短編小説 – 地球消滅
- 2025.03.21
- 小説

太陽が地平線に沈み、空が深い藍色に染まる頃、世界の終焉を告げる鐘が鳴り響いた。その音は人々の心に直接響き渡り、誰もがその意味を直感的に理解した。
科学者たちは何十年も前からこの瞬間を予測していたが、誰もその正確な日付や時間を特定することはできなかった。そして今、その「時」が訪れたのだ。
崩壊の兆し
20世紀末から21世紀初頭にかけて、地球は急速に変化していた。
気候変動、環境破壊、生物多様性の喪失。これらの問題はすべて、地球規模での「システムの限界」を示していた。しかし、それ以上に恐ろしい現象が徐々に明らかになりつつあった。それは、宇宙からの「異常信号」だった。
2027年、天文学者たちは地球外からの微弱な電波を初めて観測した。当初、それは単なる自然現象と考えられていた。しかし、その信号は周期的であり、さらに解析を進めると、それが「警告」を意味するパターンを持つことが判明した。
信号はこう告げていた。
「あなたたちの星は限界点を超えた。崩壊は不可避である。」
世界の反応
この情報が公表されると、世界中でパニックが広がった。盗み、暴動はもちろん、世界中の人々が荒れた。
なかにはその信号が真実であるかどうかを疑い、政府や科学者たちに説明を求めた。しかし、科学的な解析が進むにつれ、その信号が嘘ではないことが確定された。
地球そのものが「自己崩壊」のプロセスに入っているという結論に至ったのだ。
原因は複雑だった。地球内部のマントル活動の異常、磁場の急速な減衰、そして人類活動による環境負荷の蓄積。これらが重なり合い、「臨界点」を超えた結果、地球自体がそのバランスを維持できなくなっていた。
最後の日々
科学者たちは残された時間を計算し、正確な崩壊のタイムラインを発表した。その日付は2035年12月31日。人類にはあと8年しか残されていなかった。
この発表を受けて、各国政府は協力して「最後の計画」を立案した。
その計画とは、人類の一部を宇宙へ脱出させる「新天地移住プロジェクト」だった。
しかし、この計画には重大な制約があった。限られた資源と時間の中で、宇宙船に乗れる人数は全人類のわずか1%にも満たなかった。
そのため、人類史上最大規模の選別プロセスが行われた。科学者、医師、技術者など、いわゆる「人類存続に貢献できる人材」が優先された。
一方で、多くの人々は地球に残される運命を受け入れるしかなかった。
最後の夜
2035年12月31日。その日は静かに訪れた。
空は不気味なほど透明で、星々がいつもより輝いて見えた。地球上のすべての生物が、その異様な静けさを感じ取っていた。
宇宙へ脱出した人々は、地球を離れる瞬間までその姿を見つめていた。一方で地上に残された人々は、それぞれの方法で最後の時を迎えていた。
家族と共に過ごす者、祈りを捧げる者、ただ静かに空を見上げる者。それぞれが自分なりの「終わり」を受け入れていた。
そして、午前0時。その瞬間、地球全体が激しい振動に包まれた。大陸が裂け、大気が燃え上がり、海洋が蒸発していく。それはまるで壮大な花火のようでもあり、同時に恐ろしく静かな終焉でもあった。
新たな希望
宇宙船から見下ろす人々は、その光景を目に焼き付けながらも、新天地への旅路を進めていた。彼らは知っていた。この先には未知の困難が待ち受けているだろうと。しかし、それでも彼らは希望を持ち続けた。
「人類」という種を存続させるために。
こうして地球という惑星は歴史から姿を消した。しかし、その記憶と教訓は、新たなる星で再び芽吹く可能性を秘めている。消滅とは終わりではなく、新たな始まりでもあるのだ。
そして、人類はその新しい星で再び問いかけるだろう。
「私たちは、この星を守れるだろうか?」と。
「また同じことを繰り返すのではないのだろうか…」と。こうなる前にもっと努力していれば長生きできたのでは…
あとがき
画像の加工を無駄に努力してみたw


ちなみに元画像がこちら。比較すると歴然でしょ?
雷と大雨、あと煙を入れたらさらに崩壊風にして完成させた。
見出し画像の雷の加工はPhotoshopの雲模様1と雲模様2を使用し、そこからさらに雷風に加工。
大雨は黒ベースにノイズをしてブレを追加。それをスクリーンにすればあっとゆーまに。
煙はブラシでテキトーにポチポチ。
え? 画像の話はどうでもいい? いやいやw 皆さんに読んでもらえるように画像で惹きつける努力はしないとw なるべくそれに近い画像を使わないとw
…嘘です。小説のネタが尽きてきたんで画像で遊んでいただけですorz
- 長編小説 – ようこそ! AIしか存在していない異世界へ
- 長編小説 – 転生した春の音
- 長編小説 – 異世界への招待状 おじさんはそれなりにがんばる
- 短編小説 – 夏の1ページ
- 短編小説 – イニチャリD ~ 峠の疾風:自転車レーサーたちの物語 ~
- 短編小説 – メッセージ
- 短編小説 – 夢への挑戦
- 短編小説 – サイバーシャドウ
- 短編小説 – 雨の日の約束
- 短編小説 – FPSゲーマーの挑戦
- 短編小説 – 帰り道の出会い
- 短編小説 – マグニチュード7.5
- 短編小説 – 小さな町のパン屋さん
- 短編小説 – 大きな桜の木の下で
- 短編小説 – 風の囁(ささや)き
- 短編小説 – 命が吹き込まれたスリッパ
- 短編小説 – 消えた動画配信者
- 短編小説 – 幽霊屋敷
- 短編小説 – 地球消滅
- 短編小説 – VRが紡ぐ新たな現実
- 長編小説 – デスゲーム
- 短編小説 – ある一匹の猫の物語
- 短編小説 – 不可解な田舎町
- 短編小説 – 特売キャベツ
- 短編小説 – 世代を超えた友情
- 短編小説 – 星降る夜の秘密
-
前の記事

短編小説 – VRが紡ぐ新たな現実 2025.03.20
-
次の記事

短編小説 – 幽霊屋敷 2025.03.22




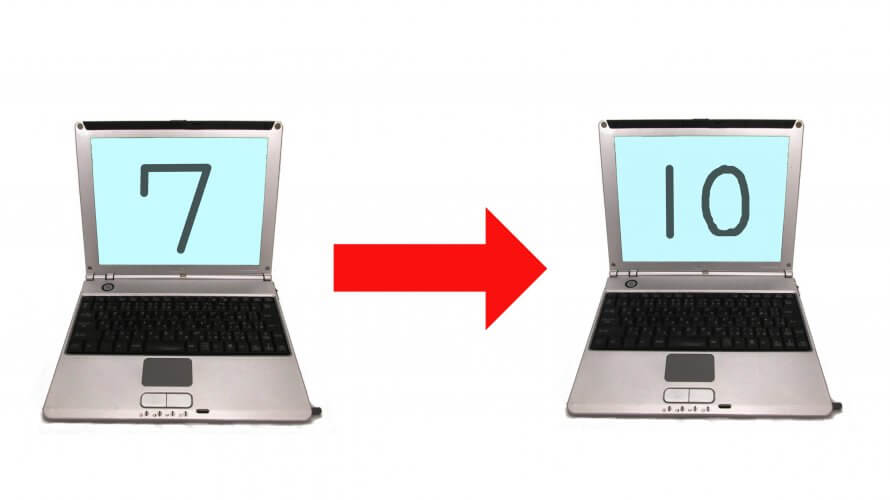




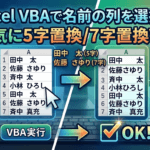


コメントを書く