長編小説 – 転生した春の音

縦書きに変更。暇つぶしにどうぞ(文章量的に大体30分程度で読み切れます)
目次
第一章:春の音、散る
小田春音(おだ はるね)は、その名の通り春の陽だまりを凝縮して人の形にしたような女性だった。
彼女がそこにいるだけで場の空気はふわりと一度、温められてから人の肺腑に届くような、そんな不思議な温かみがあった。出版社「ひだまり書房」の児童書編集部で働く彼女は、子供たちの夢や空想を形にする仕事に心からの情熱を注いでいた。作家が紡ぎ出す言葉の海に潜り、画家が描く色彩の森を彷徨い、まだ見ぬ小さな読者の心を揺さぶる一冊を世に送り出す。それが彼女の天職であり生きがいだった。校正刷りのインクの匂い、刷り上がったばかりの新刊の紙の香り、そして子供たちの弾けるような笑顔。それらが春音の世界を構成するかけがえのない要素だった。一方、上本洋介(うえもと ようすけ)は、春音とは対照的な静謐な冬の湖を思わせる男性だった。
都心に自身の設計事務所を構える彼は、若手ながらもその才能を高く評価されている建築士だった。彼の手から生み出される建築物は華美な装飾を一切排し、光と影、線と面だけで構成された研ぎ澄まされた機能美を宿していた。無駄な言葉を嫌い、口数は極端に少ない。しかし、その静けさの奥には燃えるような情熱とクライアントの想いを形にしようとする真摯な姿勢が隠されていることを、彼と仕事をした者は誰もが知っていた。彼の設計する空間はただの箱ではなく、そこに住まう人々の生活を、人生を、静かに、そして力強く支えるための「器」だった。二人の軌道が交わったのは、ある秋の日の午後だった。春音が担当する絵本作家、月島雫の個展が、表参道に新しくオープンしたギャラリー「Lumiere Claire(ルミエール・クレール)」で開催されることになったのだ。春音は、そのギャラリーに足を踏み入れた瞬間息を飲んだ。コンクリート打ちっぱなしの壁は、無機質でありながら冷たさを感じさせず、むしろキャンバスとして、これから飾られるであろう作品を待っているかのようだった。そして何より彼女を感動させたのは、巧みに計算された天窓から降り注ぐ柔らかな自然光だった。光は、時間と共にその角度を変え、壁に、床に、様々な表情の影を描き出す。それはまるで、ギャラリーそのものが呼吸しているかのようだった。
「すごい⋯⋯。この空間、月島先生の絵の世界観にぴったりだわ。光が絵に命を吹き込んでくれるみたい」
オープニングパーティーの喧騒の中、春音はシャンパングラスを片手に設計者を探した。会場の隅で誰とも話すことなく、壁に飾られた絵を静かに見つめている男性がいた。名札には「上本洋介」と記されている。彼が、この魔法のような空間の創造主だった。
「あの、設計された上本さん、ですよね? 私、ひだまり書房の小田と申します。このギャラリー本当に素晴らしいです。特に、この光の取り込み方、感動しました」
興奮気味に、半ば一方的に話しかける春音に洋介は少し驚いたように目を向けた。そして彼女の言葉が、ただのお世辞ではないこと、心からの賞賛であることを、その真剣な瞳から感じ取った。
「⋯⋯ありがとうございます。光は建物の魂ですから」
ぽつりと、しかし確信に満ちたその一言が春音の心に深く、心地よく響いた。建築における彼の哲学が、その短い言葉の中に凝縮されていた。この人は本当にこの空間を愛し、考え抜いて創り上げたのだ。その日から二人は自然と惹かれ合うように、会う時間を重ねていった。
休日のたびに二人は様々な場所へ出かけた。話題の美術館、古びた名建築、あるいは名前も知らないような街角の趣のある坂道。春音は洋介の隣で、いつもと違う世界の切り取り方を学んだ。建物の構造、素材の質感、光と影が織りなす詩。洋介の専門的な解説は、春音にとって新しい物語を読むように、刺激的で楽しかった。一方、洋介は春音の柔らかな感性に触れることで、自分のこの世界が彩られていくのを感じていた。彼は今まで建物を「構造」や「機能」で見ていたが、春音はそこに「物語」を見出す。窓から見える景色、そこに住む人の笑い声、壁に残された小さな傷。その一つ一つに、春音は物語を見つけ、楽しそうに洋介に語って聞かせた。
「このレンガの壁、一つ一つ色が違うの、面白いね。きっと、焼かれた窯も、職人さんの手の癖も、違ったんだろうな。百年後もこうして誰かが見上げてくれるなんて、レンガたちも思ってなかったかもね」
そんな春音の言葉を聞くたびに、洋介の無機質だった世界に、温かな血が通っていくようだった。仕事のプレッシャーで凝り固まった彼の心は、春音の屈託のない笑顔と、陽だまりのような温かさで、優しく解きほぐされていった。彼の孤独な世界に、春の音が聞こえてきた瞬間だった。春音もまた、洋介の多くを語らない優しさと、その奥にある深い情熱に絶対的な安心感を覚えていた。彼の隣は、どんな嵐からも守ってくれる、世界で一番安全な避難所のように思えた。
付き合い始めて二年が経った春の日。洋介は春音を、満開の桜がトンネルを作る公園へと誘った。風が吹くたびに薄紅色の花びらが雪のように舞い散る。その幻想的な光景の中で洋介は、いつもより少しだけ緊張した面持ちで春音に向き直った。
「春音」
彼が真剣な声で自分の名前を呼ぶ。春音は、これから彼が何を言おうとしているのかを察し、心臓が大きく高鳴っているのを感じた。
「俺と結婚してください。君のいない人生はもう考えられない。俺が設計する家に、君に住んでほしい。君の笑顔が俺の創る空間の最後のピースなんだ」
建築士である彼らしい、実直で心のこもったプロポーズ。春音の大きな瞳から、ぽろぽろと涙がこぼれ落ちた。それは悲しみの涙ではなく、幸福が満ち溢れて、器からこぼれ落ちた雫だった。彼女は、何度も、何度も、首を縦に振った。舞い散る桜の花びらが二人を祝福するように優しく包み込んでいた。
その日から二人の毎日は結婚式の準備という、甘く幸福な喧騒に満たされた。ウエディングドレスを選ぶために、何軒ものショップを巡った。鏡の前で慣れないドレスにはにかむ春音の姿を、洋介は少し照れくさそうに、しかし何よりも愛おしそうに見つめていた。式場は二人が出会ったあのギャラリーに決めた。オーナーは二人の馴れ初めを聞くと、快く場所を提供してくれた。招待状のデザインは洋介がシンプルな線画を描き、春音がお気に入りの絵本から引用した愛の言葉を添えた。一つ一つの作業が、二人の未来をゆっくりと、しかし確実に形作っていく。それは幸せそのものを設計していくような至福の時間だった。
そして結婚式の前日。
春音は式場での最終打ち合わせを終え、夕暮れの道を一人歩いていた。手には明日のためのブーケが、フローリストから手渡されたばかりで瑞々しい花の香りを放っている。白いバラと、かすみ草。洋介が春音に一番似合うと言って選んでくれた花だ。
彼女の頭の中は、明日からの新しい生活への期待でピンク色に染まっていた。明日、この道を今度は一人ではなく、洋介と共に歩くのだ。彼の隣で同じ苗字を名乗り、同じ家に帰り、同じ食卓を囲む。そんな夢にまで見た未来が、もうすぐそこに。そう思うと自然と笑みがこぼれ、スキップしたいような気分だった。
横断歩道の信号が青に変わる。春音は幸福な未来へ向かうように、軽やかな足取りで一歩を踏み出した。
その時だった。
けたたましいブレーキ音。タイヤがアスファルトを削る、耳を塞ぎたくなるような不協和音。そして、全てを打ち砕く鈍い衝撃音。
春音の体は、まるでスローモーション映像のように、ふわりと宙を舞った。彼女の手から滑り落ちたブーケの白い花びらが燃えるような夕暮れの空に、鮮血のように鮮やかに舞い散った。
次に彼女の意識が捉えたのは無機質な病院の白い天井と、消毒液の匂いだった。体の感覚はなく、ただ遠くで誰かが自分の名前を絶叫している声が聞こえる。洋介の声だ。泣き叫び、懇願するような彼の悲痛な声。
ごめんなさい、洋介。明日、一緒にバージンロードを歩けなくなっちゃった。ごめんなさい。あなたのためのウエディングドレス、着てあげられなくて。ごめんなさい。あなたの創ってくれた家で、あなたのご飯、作ってあげられなくて。ごめんなさい、ごめんなさい⋯⋯。
心の中で何度も謝りながら、春音の意識は、ゆっくりと深い闇の中へと沈んでいった。彼女の短い人生は、その幸福の絶頂で、あまりにも突然に幕を閉じた。
洋介にとって、春音のいない世界は色彩を失ったモノクロームの世界だった。いや、モノクロームですらなかった。光も、影も、形も、全てが意味を失った、完全な「無」だった。彼女の笑顔も、弾むような声も、陽だまりのような温もりも、もうどこにもない。設計中の図面を見ても、そこに春音の喜ぶ顔を思い描くことができなければ、それはただの線の集合体に過ぎなかった。春音との思い出が詰まった部屋は、宇宙のようにひたすらに広く、冷たく、彼の心を凍らせていった。
友人や家族が、代わる代わる彼を訪れ、慰めの言葉をかけたが、そのどれもが分厚いガラスの壁に阻まれて、彼の心には届かなかった。
春音が亡くなってから一週間。季節は春のままだった。しかし、洋介の世界だけは永遠の冬に閉ざされてしまった。彼は春音と共に住むはずだった新居の設計図を静かに燃やした。そしてあの日、春音が落とした、少しだけ形が崩れ、乾いてしまった白いバラのブーケをそっと胸に抱いた。
翌日、彼は建設中の高層ビルの屋上からその身を投げた。春音のいない世界に生きる意味など見出せなかった。せめて魂だけでも、彼女のそばに。そう願って⋯⋯
小田春音は真っ暗闇の中にいた。すると、ふと目の前に光が差した。目を覚ました時、彼女は柔らかな光の粒子が舞う、幻想的な空間にいた。目の前には見たこともないような巨木が天を突き、エメラルド色に輝く苔が大地を覆っている。自分の体を見下ろすと、そこには月光を浴びたように白く透き通る肌と、長く、そして優雅な曲線を描く尖った耳があった。簡素だが上質な生地で作られた緑色の衣を身にまとっている。
エルフ。
その言葉が知識としてではなく、本能として自然と頭に浮かんだ。どうやら自分は死んで異世界に転生したらしい。しかも人間ではなくエルフとして。混乱する頭で、春音は自分が死んだ瞬間のことを鮮明に思い出した。そして、洋介の、あの絶叫を。
彼はどうしただろうか。私のいない世界で、ちゃんと生きていてくれるだろうか。いや、あの人なら、きっと⋯⋯。不安が胸をよぎる。彼もこの世界のどこかに転生しているのではないか。そんな、あまりにも淡く、しかし切実な期待を抱かずにはいられなかった。
春音は、エルフの少女エリアーナとして悠久の時を生きる、新たな生を歩み始めた。エルフの時間は人間のそれとは比べ物にならないほどゆっくりと、そして静かに流れていく。森の仲間たちに助けられながら、エリアーナはエルフとしての生き方を一つ一つ学んでいった。風の囁きに耳を澄まし、精霊と語らい、治癒の魔法を操る。最初は戸惑うことばかりだったが、彼女の中に眠る「春音」としての順応性と優しさは、エルフの世界にも自然と溶け込んでいった。
しかし、彼女の心の奥底には常に洋介の存在があった。彼の面影は時間の経過と共に、少しずつ輪郭がぼやけていく。それでも彼を愛した記憶だけは、魂に刻まれた傷のように決して消えることはなかった。
時は流れエリアーナがエルフとして、百数年の時を孤独と共に過ごしていたある日のこと、彼女が住む「忘れられた森」の境界近くに、人間たちが新たな国を築き始めた。そして、その国に上本洋介という名の人間が、前世と同じく建築の才能を持って転生してくる事となる。彼女はまだ、その事は知る由もなかった。
二人の運命の歯車が百年の時を経て、再びゆっくりと、そして切なく、軋みを上げながら動き出そうとしていた。
彼女がそこにいるだけで場の空気はふわりと一度、温められてから人の肺腑に届くような、そんな不思議な温かみがあった。出版社「ひだまり書房」の児童書編集部で働く彼女は、子供たちの夢や空想を形にする仕事に心からの情熱を注いでいた。作家が紡ぎ出す言葉の海に潜り、画家が描く色彩の森を彷徨い、まだ見ぬ小さな読者の心を揺さぶる一冊を世に送り出す。それが彼女の天職であり生きがいだった。校正刷りのインクの匂い、刷り上がったばかりの新刊の紙の香り、そして子供たちの弾けるような笑顔。それらが春音の世界を構成するかけがえのない要素だった。一方、上本洋介(うえもと ようすけ)は、春音とは対照的な静謐な冬の湖を思わせる男性だった。
都心に自身の設計事務所を構える彼は、若手ながらもその才能を高く評価されている建築士だった。彼の手から生み出される建築物は華美な装飾を一切排し、光と影、線と面だけで構成された研ぎ澄まされた機能美を宿していた。無駄な言葉を嫌い、口数は極端に少ない。しかし、その静けさの奥には燃えるような情熱とクライアントの想いを形にしようとする真摯な姿勢が隠されていることを、彼と仕事をした者は誰もが知っていた。彼の設計する空間はただの箱ではなく、そこに住まう人々の生活を、人生を、静かに、そして力強く支えるための「器」だった。二人の軌道が交わったのは、ある秋の日の午後だった。春音が担当する絵本作家、月島雫の個展が、表参道に新しくオープンしたギャラリー「Lumiere Claire(ルミエール・クレール)」で開催されることになったのだ。春音は、そのギャラリーに足を踏み入れた瞬間息を飲んだ。コンクリート打ちっぱなしの壁は、無機質でありながら冷たさを感じさせず、むしろキャンバスとして、これから飾られるであろう作品を待っているかのようだった。そして何より彼女を感動させたのは、巧みに計算された天窓から降り注ぐ柔らかな自然光だった。光は、時間と共にその角度を変え、壁に、床に、様々な表情の影を描き出す。それはまるで、ギャラリーそのものが呼吸しているかのようだった。
「すごい⋯⋯。この空間、月島先生の絵の世界観にぴったりだわ。光が絵に命を吹き込んでくれるみたい」
オープニングパーティーの喧騒の中、春音はシャンパングラスを片手に設計者を探した。会場の隅で誰とも話すことなく、壁に飾られた絵を静かに見つめている男性がいた。名札には「上本洋介」と記されている。彼が、この魔法のような空間の創造主だった。
「あの、設計された上本さん、ですよね? 私、ひだまり書房の小田と申します。このギャラリー本当に素晴らしいです。特に、この光の取り込み方、感動しました」
興奮気味に、半ば一方的に話しかける春音に洋介は少し驚いたように目を向けた。そして彼女の言葉が、ただのお世辞ではないこと、心からの賞賛であることを、その真剣な瞳から感じ取った。
「⋯⋯ありがとうございます。光は建物の魂ですから」
ぽつりと、しかし確信に満ちたその一言が春音の心に深く、心地よく響いた。建築における彼の哲学が、その短い言葉の中に凝縮されていた。この人は本当にこの空間を愛し、考え抜いて創り上げたのだ。その日から二人は自然と惹かれ合うように、会う時間を重ねていった。
休日のたびに二人は様々な場所へ出かけた。話題の美術館、古びた名建築、あるいは名前も知らないような街角の趣のある坂道。春音は洋介の隣で、いつもと違う世界の切り取り方を学んだ。建物の構造、素材の質感、光と影が織りなす詩。洋介の専門的な解説は、春音にとって新しい物語を読むように、刺激的で楽しかった。一方、洋介は春音の柔らかな感性に触れることで、自分のこの世界が彩られていくのを感じていた。彼は今まで建物を「構造」や「機能」で見ていたが、春音はそこに「物語」を見出す。窓から見える景色、そこに住む人の笑い声、壁に残された小さな傷。その一つ一つに、春音は物語を見つけ、楽しそうに洋介に語って聞かせた。
「このレンガの壁、一つ一つ色が違うの、面白いね。きっと、焼かれた窯も、職人さんの手の癖も、違ったんだろうな。百年後もこうして誰かが見上げてくれるなんて、レンガたちも思ってなかったかもね」
そんな春音の言葉を聞くたびに、洋介の無機質だった世界に、温かな血が通っていくようだった。仕事のプレッシャーで凝り固まった彼の心は、春音の屈託のない笑顔と、陽だまりのような温かさで、優しく解きほぐされていった。彼の孤独な世界に、春の音が聞こえてきた瞬間だった。春音もまた、洋介の多くを語らない優しさと、その奥にある深い情熱に絶対的な安心感を覚えていた。彼の隣は、どんな嵐からも守ってくれる、世界で一番安全な避難所のように思えた。
付き合い始めて二年が経った春の日。洋介は春音を、満開の桜がトンネルを作る公園へと誘った。風が吹くたびに薄紅色の花びらが雪のように舞い散る。その幻想的な光景の中で洋介は、いつもより少しだけ緊張した面持ちで春音に向き直った。
「春音」
彼が真剣な声で自分の名前を呼ぶ。春音は、これから彼が何を言おうとしているのかを察し、心臓が大きく高鳴っているのを感じた。
「俺と結婚してください。君のいない人生はもう考えられない。俺が設計する家に、君に住んでほしい。君の笑顔が俺の創る空間の最後のピースなんだ」
建築士である彼らしい、実直で心のこもったプロポーズ。春音の大きな瞳から、ぽろぽろと涙がこぼれ落ちた。それは悲しみの涙ではなく、幸福が満ち溢れて、器からこぼれ落ちた雫だった。彼女は、何度も、何度も、首を縦に振った。舞い散る桜の花びらが二人を祝福するように優しく包み込んでいた。
その日から二人の毎日は結婚式の準備という、甘く幸福な喧騒に満たされた。ウエディングドレスを選ぶために、何軒ものショップを巡った。鏡の前で慣れないドレスにはにかむ春音の姿を、洋介は少し照れくさそうに、しかし何よりも愛おしそうに見つめていた。式場は二人が出会ったあのギャラリーに決めた。オーナーは二人の馴れ初めを聞くと、快く場所を提供してくれた。招待状のデザインは洋介がシンプルな線画を描き、春音がお気に入りの絵本から引用した愛の言葉を添えた。一つ一つの作業が、二人の未来をゆっくりと、しかし確実に形作っていく。それは幸せそのものを設計していくような至福の時間だった。
そして結婚式の前日。
春音は式場での最終打ち合わせを終え、夕暮れの道を一人歩いていた。手には明日のためのブーケが、フローリストから手渡されたばかりで瑞々しい花の香りを放っている。白いバラと、かすみ草。洋介が春音に一番似合うと言って選んでくれた花だ。
彼女の頭の中は、明日からの新しい生活への期待でピンク色に染まっていた。明日、この道を今度は一人ではなく、洋介と共に歩くのだ。彼の隣で同じ苗字を名乗り、同じ家に帰り、同じ食卓を囲む。そんな夢にまで見た未来が、もうすぐそこに。そう思うと自然と笑みがこぼれ、スキップしたいような気分だった。
横断歩道の信号が青に変わる。春音は幸福な未来へ向かうように、軽やかな足取りで一歩を踏み出した。
その時だった。
けたたましいブレーキ音。タイヤがアスファルトを削る、耳を塞ぎたくなるような不協和音。そして、全てを打ち砕く鈍い衝撃音。
春音の体は、まるでスローモーション映像のように、ふわりと宙を舞った。彼女の手から滑り落ちたブーケの白い花びらが燃えるような夕暮れの空に、鮮血のように鮮やかに舞い散った。
次に彼女の意識が捉えたのは無機質な病院の白い天井と、消毒液の匂いだった。体の感覚はなく、ただ遠くで誰かが自分の名前を絶叫している声が聞こえる。洋介の声だ。泣き叫び、懇願するような彼の悲痛な声。
ごめんなさい、洋介。明日、一緒にバージンロードを歩けなくなっちゃった。ごめんなさい。あなたのためのウエディングドレス、着てあげられなくて。ごめんなさい。あなたの創ってくれた家で、あなたのご飯、作ってあげられなくて。ごめんなさい、ごめんなさい⋯⋯。
心の中で何度も謝りながら、春音の意識は、ゆっくりと深い闇の中へと沈んでいった。彼女の短い人生は、その幸福の絶頂で、あまりにも突然に幕を閉じた。
洋介にとって、春音のいない世界は色彩を失ったモノクロームの世界だった。いや、モノクロームですらなかった。光も、影も、形も、全てが意味を失った、完全な「無」だった。彼女の笑顔も、弾むような声も、陽だまりのような温もりも、もうどこにもない。設計中の図面を見ても、そこに春音の喜ぶ顔を思い描くことができなければ、それはただの線の集合体に過ぎなかった。春音との思い出が詰まった部屋は、宇宙のようにひたすらに広く、冷たく、彼の心を凍らせていった。
友人や家族が、代わる代わる彼を訪れ、慰めの言葉をかけたが、そのどれもが分厚いガラスの壁に阻まれて、彼の心には届かなかった。
春音が亡くなってから一週間。季節は春のままだった。しかし、洋介の世界だけは永遠の冬に閉ざされてしまった。彼は春音と共に住むはずだった新居の設計図を静かに燃やした。そしてあの日、春音が落とした、少しだけ形が崩れ、乾いてしまった白いバラのブーケをそっと胸に抱いた。
翌日、彼は建設中の高層ビルの屋上からその身を投げた。春音のいない世界に生きる意味など見出せなかった。せめて魂だけでも、彼女のそばに。そう願って⋯⋯
小田春音は真っ暗闇の中にいた。すると、ふと目の前に光が差した。目を覚ました時、彼女は柔らかな光の粒子が舞う、幻想的な空間にいた。目の前には見たこともないような巨木が天を突き、エメラルド色に輝く苔が大地を覆っている。自分の体を見下ろすと、そこには月光を浴びたように白く透き通る肌と、長く、そして優雅な曲線を描く尖った耳があった。簡素だが上質な生地で作られた緑色の衣を身にまとっている。
エルフ。
その言葉が知識としてではなく、本能として自然と頭に浮かんだ。どうやら自分は死んで異世界に転生したらしい。しかも人間ではなくエルフとして。混乱する頭で、春音は自分が死んだ瞬間のことを鮮明に思い出した。そして、洋介の、あの絶叫を。
彼はどうしただろうか。私のいない世界で、ちゃんと生きていてくれるだろうか。いや、あの人なら、きっと⋯⋯。不安が胸をよぎる。彼もこの世界のどこかに転生しているのではないか。そんな、あまりにも淡く、しかし切実な期待を抱かずにはいられなかった。
春音は、エルフの少女エリアーナとして悠久の時を生きる、新たな生を歩み始めた。エルフの時間は人間のそれとは比べ物にならないほどゆっくりと、そして静かに流れていく。森の仲間たちに助けられながら、エリアーナはエルフとしての生き方を一つ一つ学んでいった。風の囁きに耳を澄まし、精霊と語らい、治癒の魔法を操る。最初は戸惑うことばかりだったが、彼女の中に眠る「春音」としての順応性と優しさは、エルフの世界にも自然と溶け込んでいった。
しかし、彼女の心の奥底には常に洋介の存在があった。彼の面影は時間の経過と共に、少しずつ輪郭がぼやけていく。それでも彼を愛した記憶だけは、魂に刻まれた傷のように決して消えることはなかった。
時は流れエリアーナがエルフとして、百数年の時を孤独と共に過ごしていたある日のこと、彼女が住む「忘れられた森」の境界近くに、人間たちが新たな国を築き始めた。そして、その国に上本洋介という名の人間が、前世と同じく建築の才能を持って転生してくる事となる。彼女はまだ、その事は知る由もなかった。
二人の運命の歯車が百年の時を経て、再びゆっくりと、そして切なく、軋みを上げながら動き出そうとしていた。
第二章:百年の孤独、刹那の再会
エリアーナとして生を受けて、百二十度目の春が訪れようとしていた。忘れられた森では、時間の流れ方が外界とは異なる。それは単なる比喩ではなく、森そのものが悠久の時を内包し、そこに住まう者たちの心拍すらも、ゆったりとしたリズムに調律してしまうかのようだった。エルフにとって百年という歳月は、人間が季節の移ろいを数えるのに似て、さして大きな意味を持たない。新たな若葉が芽吹き、やがて朽ちて土に還る。その繰り返しの果てに、また新しい緑が生まれる。ただそれだけの、自然の摂理の一部だった。
しかし、エリアーナの中に眠る「小田春音」の魂は、その悠然とした時の流れに、完全には溶け込むことができずにいた。百二十年。人間の尺度で言えば、一人の人間が生まれ、老い、その生を全うし、さらにその子供や孫の代までをも見届けるに足る長大な時間だ。その歳月の中で、春音としての記憶は、まるで長い風雨に晒された石碑のように少しずつ、しかし確実に摩耗していった。
洋介の、あの実直な声。プロポーズの時に少しだけ上擦っていた愛おしい響き。思い出そうとしても霧の向こうから聞こえてくるようで、鮮明には蘇らない。彼の大きな手。ごつごつとして、けれど温かかった、あの手の感触。それも、今となっては夢の中で触れたかのような、曖昧な記憶の残滓でしかなかった。楽しかったデートの記憶も、喧嘩した日の気まずさも、結婚式の準備に胸を躍らせた日々も、まるで分厚いアルバムのページを一枚一枚めくっていくように色褪せ、そのディテールを失いつつあった。
それでも、ただ一つ、決して風化することのないものがあった。
彼の魂を愛している、という、その根源的な感情だけは百二十年の時を経てもなお、彼女の魂の中心で静かな熱を放ち続けていた。それはもはや記憶というよりは、彼女という存在を構成する、不可分の要素となっていた。洋介を想うこと。それはエリアーナにとって、呼吸をすることと同義だった。
彼女は、エルフの中でも特に優れた治癒魔法の使い手となっていた。その両手から放たれる柔らかな金色の光は、どんな傷も癒し、どんな病も和らげる力を持っていた。毒蛇に咬まれた若鹿を救い、嵐で枝を折られた古木を労り、病に苦しむ同胞がいれば夜を徹してその傍らに寄り添った。彼女の周りには、いつも穏やかで慈愛に満ちた空気が流れ、森の仲間たちは深い敬愛の念を込めて、彼女を「癒し手様」と呼んだ。
だが、仲間たちが知る由もなかった。他者を癒せば癒すほど、エリアーナ自身の心にある癒えない傷口が、疼くようにその存在を主張することを。傷ついた生き物の中に、あの日の自分の姿を重ねてしまうことを。そして、癒しの光を放ちながら、彼女の心は常に、たった一人の男の面影を追い求めていることを。
「エリアーナ、また遠くを見ている。お前の魂は、半分、ここにはないようだ」
背後からかけられた声に、エリアーナはハッと我に返った。振り返ると、そこには森の長老であるエルドランが、深い叡智を湛えた瞳で彼女を見つめていた。彼の樹皮のように皺深い顔は、この森の歴史そのものを物語っている。エリアーナがエルフとして生まれ落ちた時から、彼は父親のように、あるいはそれ以上の存在として、彼女を見守り続けてきた。
「エルドラン様⋯⋯。申し訳ありません、少し考え事をしておりました」
「考え事か。それとも、思い出に浸っていたのか。お前が『昔』と呼ぶ、ほんの瞬きほどの時間のことだ」
エルドランの言葉は、いつも真理を突いてくる。エリアーナは反論も言い訳もできず、ただ黙って俯いた。足元の苔が、露を含んでしっとりと輝いている。
「忘れられないか。人間としての、あの短い生を。そして、その想い人を」
「⋯⋯忘れたく、ないのです」
エリアーナは、絞り出すように言った。
「忘れてしまったら、本当に、彼との全てが、無かったことになってしまいそうで。この想いだけが、私が『小田春音』であったことの、唯一の証なのです」
「証、か」
エルドランは静かに息をついた。
「執着とも言う。我らエルフは過去に生きない。未来も憂えない。ただ、今ここに吹く風を感じ、木々の歌に耳を澄ませる。時の流れに身を委ねることで、永遠を生きるのだ。だが、お前は時の流れに抗おうとしている。それは、自ら茨の道を歩むに等しい」
「分かっています。でも、私にはできないのです」
「時の流れは残酷なようでいて、慈悲深くもある。全てを洗い流し、やがては平らにしてくれる。いつか、お前の心の傷も癒える日が来るだろう」
エルドランはそう言って、エリアーナの肩を優しく叩いた。しかし、エリアーナは、その傷が癒えることを望んでいなかった。洋介を忘れることは、彼との愛を、あの幸福だった日々を、自ら否定することのように思えたからだ。この痛みこそが、彼を愛した証なのだと、彼女は頑なに信じていた。
そんなある日、森に、これまでとは質の違う不穏な空気が流れ始めた。忘れられた森の南の境界。そこは緩やかな丘陵地帯となっており、人間たちの領域とは、暗黙の内に隔てられていた場所だった。その丘の向こうから、木が倒れる音、金属を打つ音、そして人々の喧騒が、風に乗って微かに聞こえてくるようになったのだ。
人間たちが、森の境界近くに、新たな住処を建設し始めたのだ。
森の精霊たちは、土を汚す鉄の匂いを嫌い姿を隠した。臆病な森の動物たちは、けたたましい音に怯え、森の奥深くへと逃げ込んでいく。エルフたちの間にも、動揺が広がった。
「人間どもめ、我らの聖域を侵す気か」
「今のうちに、警告を与えて追い払うべきだ」
強硬な意見を口にする者も少なくなかった。人間という種族が、いかに短絡的で、破壊を好むかを、エルフたちは長い歴史の中で知っていたからだ。
エリアーナは、言いようのない胸騒ぎを覚え、自らの目で確かめるために、南の境界へと向かった。何百年も足を踏み入れたことのない、森の辺境。鬱蒼とした木々を抜け、視界が開けた瞬間、彼女は丘の上で息を飲んだ。
そこには、懸命に働く人間たちの姿があった。屈強な男たちが斧を振るって木を切り倒し、女子供は石を運び、土地をならしている。彼らは決して、森を無意味に破壊しようとしているわけではなかった。むしろ、その眼差しは真剣そのもので、自分たちの生きる場所を、未来を、その手で必死に切り拓こうとしているだけなのだ。その必死な姿は、かつて建築士として、人々の暮らしのために情熱を燃やしていた、ある男の姿と、どこか重なって見えた。
エリアーナは、木々の陰に身を潜め、無意識に彼らの様子を観察していた。何日も、何日も。開拓地は、少しずつ、しかし着実に村の形を成していった。簡素な小屋が建ち、畑が耕され、井戸が掘られた。
そして、その中心には、いつも一人の青年がいた。
彼は、他の者たちより頭一つ背が高く、日に焼けた肌はたくましかった。他の人間たちに指示を出し、自らも率先して重い木材を運び、汗を流している。彼の周りには自然と人が集まり、その的確な指示に、皆が信頼を寄せて従っているようだった。
ある日の午後、青年が仲間と共に、組み上げたばかりの家の骨組みを見上げていた。強い西日が、彼の横顔を照らし出す。その真剣な眼差し、少しだけ尖らせた唇、仕事に対する一点の曇りもない真摯なまなざし。
エリアーナは、心臓を鷲掴みにされたかのような衝撃に、その場に凍りついた。
(⋯⋯洋介⋯⋯?)
ありえない。そんなはずはない。髪の色は前世の漆黒ではなく、太陽の光を吸い込んだような明るい茶色だ。瞳の色も深い黒ではなく、森の木々と同じ穏やかな緑色をしている。顔立ちも、どこか異国の血を感じさせる彫りの深いものだ。別人だ。そうに決まっている。
だが。
魂が、叫んでいた。
あの人だ、と。
百二十年間、片時も忘れることのなかった、愛しい人の魂が、今、目の前にいると。
エリアーナは震える手で口を覆った。溢れ出しそうになる嗚咽を必死で飲み込む。木陰から飛び出し、彼の名前を叫びたい衝動に駆られたが、両足は根が生えたように動かなかった。
百年の時を経てついに再会できた。神は自分の祈りを、聞き届けてくれたのだ。喜びが津波のように全身を駆け巡った。
しかし、その直後。喜びの波が引いた後に残ったのは、喜びの何倍もの大きさを持つ、深い、深い絶望の感情だった。
今の自分は、エルフのエリアーナだ。そして彼は、人間の青年。
自分は、これから何百年、あるいは何千年と、この姿のまま生きていく。しかし、彼は、彼は、人間としての短い生涯を、あっという間に駆け抜けていってしまうだろう。やがて彼は歳をとり、顔にシワを刻み、白髪になり、そして死ぬ。
やっと会えたのに。
また死が、二人を分かつ。
それも、今度は一方的に彼だけを連れ去っていく、抗うことのできない、絶対的な別離が。
その事実に気づいた瞬間、エリアーナの世界は、喜びの光から一転して暗い絶望の闇に突き落とされた。
青年――洋介は、この異世界でも、建築の才能に恵まれていたようだった。彼が設計し仲間たちと共に建てた家は、簡素ながらも風通しや日当たりが計算され尽くした、住む人のことを第一に考えた温かみのあるものだった。村人たちは、若くして卓越したリーダーシップを発揮する彼を深く信頼し、愛していた。
エリアーナは、それから毎日、森の木陰から洋介の姿を見守り続けた。それが彼女の新たな日課となった。
彼に会いたい。一言でもいい、話がしたい。しかし、その一歩がどうしても踏み出せなかった。自分の存在が、彼の人生を、幸せを、狂わせてしまうのではないか。悠久の時を生きるエルフと、刹那の時を生きる人間。あまりにも違う二つの時間が、再び巡り会った二人を、無情にも引き裂こうとしているかのようだった。
季節は何度も巡り、村は少しずつ大きくなっていった。洋介も、たくましい青年に成長していた。そして、いつしか彼の隣には、いつも笑顔の絶えない、快活な人間の女性の姿があった。
彼女の名はリリア。村長の娘で村の誰からも愛される、太陽のような女性だった。彼女は洋介に想いを寄せており、その気持ちを隠そうともしなかった。仕事に打ち込む洋介のために、かいがいしく水の入った水差しを運び、汗を拭うための布を差し出す。そして二人は、仲間たちと共に楽しそうに笑い合うのだ。
その光景を見るたびに、エリアーナの胸は、まるで細い針で、何度も、何度も、突き刺されるように痛んだ。
春音だった頃の自分と洋介。
そしてリリアと洋介。
二つの光景が脳裏で重なる。エリアーナは自分の心の中に、黒く醜い感情が渦巻いていることに気づき愕然とした。嫉妬。百二十年もの間、彼だけを想い続けてきた。それなのに、いざ再会してみれば自分は何もできず、ただ遠くから彼が別の女性と親密になっていくのを見ていることしかできない。その無力感が彼女の心を蝕んでいった。
リリアは、自分にはないものを全て持っているように見えた。同じ人間として、同じ時間を生き、同じように歳をとり、彼を支え、やがては彼の子供を産むのだろう。それはかつて小田春音が夢見た、あまりにも眩しい幸福の形そのものだった。
ある満月の夜だった。
月光が、森を、そして人間の村を分け隔てなく青白く照らしている。エリアーナは泉の水面に映る自分の顔を見つめていた。百二十年前と何一つ変わらない、若く、美しいエルフの顔。しかし、その瞳の奥には人間の一生分よりも遥かに深い、孤独と悲しみが淀んでいた。
このまま見ているだけで本当にいいのだろうか。
このまま彼が何も知らずに別の誰かと結ばれ、その一生を終えるのを見送るだけで。
後悔しないだろうか。
いや、きっと後悔する。何百年、何千年経っても、この日の無力な自分をきっと呪い続けるだろう。
エリアーナは、ついに決心した。
一目だけでもいい。彼の声が聞きたい。そして、もし許されるなら、自分の気持ちに何らかの区切りをつけたい。たとえそれが、残酷な現実を突きつけられる結果になったとしても。
エリアーナは、音を立てないように森を出た。エルフの身体能力は、人間の比ではない。月の光だけを頼りに、彼女は風のように人間の村へと向かった。
村は夜の静寂に包まれていた。昼間の喧騒が嘘のように、家々の窓からは温かい光が漏れ、人々の穏やかな寝息が聞こえてきそうだった。エリアーナは、その光景に、前世で自分が生きていた世界の夜を思い出し、胸が締め付けられた。
彼女は洋介が住んでいるであろう、村で一番立派な、しかし華美ではない家を探し当てた。そして、そっと窓から中を覗き込んだ。
部屋の中では、洋介が大きな木の机に向かって、羊皮紙に図面を引いていた。揺れるランプの光が彼の真剣な横顔を照らしている。その姿は、前世で、夜遅くまで設計図と向き合っていた彼の姿と、寸分違わず重なった。その光景を見ただけで、エリアーナの目から堰を切ったように涙が溢れてきた。
会いたかった。
ずっと、ずっと、会いたかった。
この百二十年間、片時も忘れたことのない、愛しい人。
彼女は、嗚咽を漏らさないように、必死で唇を噛み締めた。
その時だった。
まるで、彼女の視線を感じ取ったかのように、洋介がふと、顔を上げた。
そして彼の緑色の瞳が、窓の外に佇む見慣れぬ女の姿を正確に捉えた。
月光に照らされて、銀色に輝く長い髪。人間離れした、神々しいまでの美貌。そして何よりも、その大きな瞳から大粒の涙を流しているその姿。
洋介の目が、驚きに、大きく、大きく見開かれた。
百二十年の時を超えて。
人間とエルフとして、再び出会った二人の視線が。
静寂の夜の中で、確かに交差した。
「君は⋯⋯?」
静寂を破ったのは、彼の、戸惑いに満ちた、かすれた声だった。
エリアーナは、何も言えずに、ただ、立ち尽くすだけだった。彼の声を聞いただけで、全身の力が抜けていくようだった。その声もまた、紛れもなく彼女が愛した洋介の声だったからだ。
しかし、エリアーナの中に眠る「小田春音」の魂は、その悠然とした時の流れに、完全には溶け込むことができずにいた。百二十年。人間の尺度で言えば、一人の人間が生まれ、老い、その生を全うし、さらにその子供や孫の代までをも見届けるに足る長大な時間だ。その歳月の中で、春音としての記憶は、まるで長い風雨に晒された石碑のように少しずつ、しかし確実に摩耗していった。
洋介の、あの実直な声。プロポーズの時に少しだけ上擦っていた愛おしい響き。思い出そうとしても霧の向こうから聞こえてくるようで、鮮明には蘇らない。彼の大きな手。ごつごつとして、けれど温かかった、あの手の感触。それも、今となっては夢の中で触れたかのような、曖昧な記憶の残滓でしかなかった。楽しかったデートの記憶も、喧嘩した日の気まずさも、結婚式の準備に胸を躍らせた日々も、まるで分厚いアルバムのページを一枚一枚めくっていくように色褪せ、そのディテールを失いつつあった。
それでも、ただ一つ、決して風化することのないものがあった。
彼の魂を愛している、という、その根源的な感情だけは百二十年の時を経てもなお、彼女の魂の中心で静かな熱を放ち続けていた。それはもはや記憶というよりは、彼女という存在を構成する、不可分の要素となっていた。洋介を想うこと。それはエリアーナにとって、呼吸をすることと同義だった。
彼女は、エルフの中でも特に優れた治癒魔法の使い手となっていた。その両手から放たれる柔らかな金色の光は、どんな傷も癒し、どんな病も和らげる力を持っていた。毒蛇に咬まれた若鹿を救い、嵐で枝を折られた古木を労り、病に苦しむ同胞がいれば夜を徹してその傍らに寄り添った。彼女の周りには、いつも穏やかで慈愛に満ちた空気が流れ、森の仲間たちは深い敬愛の念を込めて、彼女を「癒し手様」と呼んだ。
だが、仲間たちが知る由もなかった。他者を癒せば癒すほど、エリアーナ自身の心にある癒えない傷口が、疼くようにその存在を主張することを。傷ついた生き物の中に、あの日の自分の姿を重ねてしまうことを。そして、癒しの光を放ちながら、彼女の心は常に、たった一人の男の面影を追い求めていることを。
「エリアーナ、また遠くを見ている。お前の魂は、半分、ここにはないようだ」
背後からかけられた声に、エリアーナはハッと我に返った。振り返ると、そこには森の長老であるエルドランが、深い叡智を湛えた瞳で彼女を見つめていた。彼の樹皮のように皺深い顔は、この森の歴史そのものを物語っている。エリアーナがエルフとして生まれ落ちた時から、彼は父親のように、あるいはそれ以上の存在として、彼女を見守り続けてきた。
「エルドラン様⋯⋯。申し訳ありません、少し考え事をしておりました」
「考え事か。それとも、思い出に浸っていたのか。お前が『昔』と呼ぶ、ほんの瞬きほどの時間のことだ」
エルドランの言葉は、いつも真理を突いてくる。エリアーナは反論も言い訳もできず、ただ黙って俯いた。足元の苔が、露を含んでしっとりと輝いている。
「忘れられないか。人間としての、あの短い生を。そして、その想い人を」
「⋯⋯忘れたく、ないのです」
エリアーナは、絞り出すように言った。
「忘れてしまったら、本当に、彼との全てが、無かったことになってしまいそうで。この想いだけが、私が『小田春音』であったことの、唯一の証なのです」
「証、か」
エルドランは静かに息をついた。
「執着とも言う。我らエルフは過去に生きない。未来も憂えない。ただ、今ここに吹く風を感じ、木々の歌に耳を澄ませる。時の流れに身を委ねることで、永遠を生きるのだ。だが、お前は時の流れに抗おうとしている。それは、自ら茨の道を歩むに等しい」
「分かっています。でも、私にはできないのです」
「時の流れは残酷なようでいて、慈悲深くもある。全てを洗い流し、やがては平らにしてくれる。いつか、お前の心の傷も癒える日が来るだろう」
エルドランはそう言って、エリアーナの肩を優しく叩いた。しかし、エリアーナは、その傷が癒えることを望んでいなかった。洋介を忘れることは、彼との愛を、あの幸福だった日々を、自ら否定することのように思えたからだ。この痛みこそが、彼を愛した証なのだと、彼女は頑なに信じていた。
そんなある日、森に、これまでとは質の違う不穏な空気が流れ始めた。忘れられた森の南の境界。そこは緩やかな丘陵地帯となっており、人間たちの領域とは、暗黙の内に隔てられていた場所だった。その丘の向こうから、木が倒れる音、金属を打つ音、そして人々の喧騒が、風に乗って微かに聞こえてくるようになったのだ。
人間たちが、森の境界近くに、新たな住処を建設し始めたのだ。
森の精霊たちは、土を汚す鉄の匂いを嫌い姿を隠した。臆病な森の動物たちは、けたたましい音に怯え、森の奥深くへと逃げ込んでいく。エルフたちの間にも、動揺が広がった。
「人間どもめ、我らの聖域を侵す気か」
「今のうちに、警告を与えて追い払うべきだ」
強硬な意見を口にする者も少なくなかった。人間という種族が、いかに短絡的で、破壊を好むかを、エルフたちは長い歴史の中で知っていたからだ。
エリアーナは、言いようのない胸騒ぎを覚え、自らの目で確かめるために、南の境界へと向かった。何百年も足を踏み入れたことのない、森の辺境。鬱蒼とした木々を抜け、視界が開けた瞬間、彼女は丘の上で息を飲んだ。
そこには、懸命に働く人間たちの姿があった。屈強な男たちが斧を振るって木を切り倒し、女子供は石を運び、土地をならしている。彼らは決して、森を無意味に破壊しようとしているわけではなかった。むしろ、その眼差しは真剣そのもので、自分たちの生きる場所を、未来を、その手で必死に切り拓こうとしているだけなのだ。その必死な姿は、かつて建築士として、人々の暮らしのために情熱を燃やしていた、ある男の姿と、どこか重なって見えた。
エリアーナは、木々の陰に身を潜め、無意識に彼らの様子を観察していた。何日も、何日も。開拓地は、少しずつ、しかし着実に村の形を成していった。簡素な小屋が建ち、畑が耕され、井戸が掘られた。
そして、その中心には、いつも一人の青年がいた。
彼は、他の者たちより頭一つ背が高く、日に焼けた肌はたくましかった。他の人間たちに指示を出し、自らも率先して重い木材を運び、汗を流している。彼の周りには自然と人が集まり、その的確な指示に、皆が信頼を寄せて従っているようだった。
ある日の午後、青年が仲間と共に、組み上げたばかりの家の骨組みを見上げていた。強い西日が、彼の横顔を照らし出す。その真剣な眼差し、少しだけ尖らせた唇、仕事に対する一点の曇りもない真摯なまなざし。
エリアーナは、心臓を鷲掴みにされたかのような衝撃に、その場に凍りついた。
(⋯⋯洋介⋯⋯?)
ありえない。そんなはずはない。髪の色は前世の漆黒ではなく、太陽の光を吸い込んだような明るい茶色だ。瞳の色も深い黒ではなく、森の木々と同じ穏やかな緑色をしている。顔立ちも、どこか異国の血を感じさせる彫りの深いものだ。別人だ。そうに決まっている。
だが。
魂が、叫んでいた。
あの人だ、と。
百二十年間、片時も忘れることのなかった、愛しい人の魂が、今、目の前にいると。
エリアーナは震える手で口を覆った。溢れ出しそうになる嗚咽を必死で飲み込む。木陰から飛び出し、彼の名前を叫びたい衝動に駆られたが、両足は根が生えたように動かなかった。
百年の時を経てついに再会できた。神は自分の祈りを、聞き届けてくれたのだ。喜びが津波のように全身を駆け巡った。
しかし、その直後。喜びの波が引いた後に残ったのは、喜びの何倍もの大きさを持つ、深い、深い絶望の感情だった。
今の自分は、エルフのエリアーナだ。そして彼は、人間の青年。
自分は、これから何百年、あるいは何千年と、この姿のまま生きていく。しかし、彼は、彼は、人間としての短い生涯を、あっという間に駆け抜けていってしまうだろう。やがて彼は歳をとり、顔にシワを刻み、白髪になり、そして死ぬ。
やっと会えたのに。
また死が、二人を分かつ。
それも、今度は一方的に彼だけを連れ去っていく、抗うことのできない、絶対的な別離が。
その事実に気づいた瞬間、エリアーナの世界は、喜びの光から一転して暗い絶望の闇に突き落とされた。
青年――洋介は、この異世界でも、建築の才能に恵まれていたようだった。彼が設計し仲間たちと共に建てた家は、簡素ながらも風通しや日当たりが計算され尽くした、住む人のことを第一に考えた温かみのあるものだった。村人たちは、若くして卓越したリーダーシップを発揮する彼を深く信頼し、愛していた。
エリアーナは、それから毎日、森の木陰から洋介の姿を見守り続けた。それが彼女の新たな日課となった。
彼に会いたい。一言でもいい、話がしたい。しかし、その一歩がどうしても踏み出せなかった。自分の存在が、彼の人生を、幸せを、狂わせてしまうのではないか。悠久の時を生きるエルフと、刹那の時を生きる人間。あまりにも違う二つの時間が、再び巡り会った二人を、無情にも引き裂こうとしているかのようだった。
季節は何度も巡り、村は少しずつ大きくなっていった。洋介も、たくましい青年に成長していた。そして、いつしか彼の隣には、いつも笑顔の絶えない、快活な人間の女性の姿があった。
彼女の名はリリア。村長の娘で村の誰からも愛される、太陽のような女性だった。彼女は洋介に想いを寄せており、その気持ちを隠そうともしなかった。仕事に打ち込む洋介のために、かいがいしく水の入った水差しを運び、汗を拭うための布を差し出す。そして二人は、仲間たちと共に楽しそうに笑い合うのだ。
その光景を見るたびに、エリアーナの胸は、まるで細い針で、何度も、何度も、突き刺されるように痛んだ。
春音だった頃の自分と洋介。
そしてリリアと洋介。
二つの光景が脳裏で重なる。エリアーナは自分の心の中に、黒く醜い感情が渦巻いていることに気づき愕然とした。嫉妬。百二十年もの間、彼だけを想い続けてきた。それなのに、いざ再会してみれば自分は何もできず、ただ遠くから彼が別の女性と親密になっていくのを見ていることしかできない。その無力感が彼女の心を蝕んでいった。
リリアは、自分にはないものを全て持っているように見えた。同じ人間として、同じ時間を生き、同じように歳をとり、彼を支え、やがては彼の子供を産むのだろう。それはかつて小田春音が夢見た、あまりにも眩しい幸福の形そのものだった。
ある満月の夜だった。
月光が、森を、そして人間の村を分け隔てなく青白く照らしている。エリアーナは泉の水面に映る自分の顔を見つめていた。百二十年前と何一つ変わらない、若く、美しいエルフの顔。しかし、その瞳の奥には人間の一生分よりも遥かに深い、孤独と悲しみが淀んでいた。
このまま見ているだけで本当にいいのだろうか。
このまま彼が何も知らずに別の誰かと結ばれ、その一生を終えるのを見送るだけで。
後悔しないだろうか。
いや、きっと後悔する。何百年、何千年経っても、この日の無力な自分をきっと呪い続けるだろう。
エリアーナは、ついに決心した。
一目だけでもいい。彼の声が聞きたい。そして、もし許されるなら、自分の気持ちに何らかの区切りをつけたい。たとえそれが、残酷な現実を突きつけられる結果になったとしても。
エリアーナは、音を立てないように森を出た。エルフの身体能力は、人間の比ではない。月の光だけを頼りに、彼女は風のように人間の村へと向かった。
村は夜の静寂に包まれていた。昼間の喧騒が嘘のように、家々の窓からは温かい光が漏れ、人々の穏やかな寝息が聞こえてきそうだった。エリアーナは、その光景に、前世で自分が生きていた世界の夜を思い出し、胸が締め付けられた。
彼女は洋介が住んでいるであろう、村で一番立派な、しかし華美ではない家を探し当てた。そして、そっと窓から中を覗き込んだ。
部屋の中では、洋介が大きな木の机に向かって、羊皮紙に図面を引いていた。揺れるランプの光が彼の真剣な横顔を照らしている。その姿は、前世で、夜遅くまで設計図と向き合っていた彼の姿と、寸分違わず重なった。その光景を見ただけで、エリアーナの目から堰を切ったように涙が溢れてきた。
会いたかった。
ずっと、ずっと、会いたかった。
この百二十年間、片時も忘れたことのない、愛しい人。
彼女は、嗚咽を漏らさないように、必死で唇を噛み締めた。
その時だった。
まるで、彼女の視線を感じ取ったかのように、洋介がふと、顔を上げた。
そして彼の緑色の瞳が、窓の外に佇む見慣れぬ女の姿を正確に捉えた。
月光に照らされて、銀色に輝く長い髪。人間離れした、神々しいまでの美貌。そして何よりも、その大きな瞳から大粒の涙を流しているその姿。
洋介の目が、驚きに、大きく、大きく見開かれた。
百二十年の時を超えて。
人間とエルフとして、再び出会った二人の視線が。
静寂の夜の中で、確かに交差した。
「君は⋯⋯?」
静寂を破ったのは、彼の、戸惑いに満ちた、かすれた声だった。
エリアーナは、何も言えずに、ただ、立ち尽くすだけだった。彼の声を聞いただけで、全身の力が抜けていくようだった。その声もまた、紛れもなく彼女が愛した洋介の声だったからだ。
第三章:時のすれ違い、心の距離
百二十年の時を超えて、二人の視線が交差した。洋介の戸惑いの声が、静寂の夜気を震わせる。「君は⋯?」。その声は、エリアーナの魂に深く突き刺さり、彼女の時間を百二十年前に引き戻した。当たり前だ。彼の記憶に、「エリアーナ」というエルフは存在しない。彼の魂が覚えていたとしても、彼の脳は、目の前にいる人間ならざる美しい存在を、理解できずにいるのだ。自分は、彼にとって見知らぬ、そして少しばかり奇妙な闖入者でしかない。
「⋯⋯森の者です」
エリアーナは、喉の奥からやっとの思いで言葉を絞り出した。声が震えないように、全身の神経を集中させる。
「村の様子が気になって、少し見に来ただけ。⋯⋯お騒がせしました」
そう言って、彼女は身を翻した。一刻も早く、この場から逃げ出したかった。彼の瞳に見つめられているだけで、築き上げてきた百二十年分の理性が、砂の城のように崩れ落ちてしまいそうだったからだ。追いかけてくるな、と心の中で絶叫しながら、彼女は闇の中へと駆け出した。エルフのしなやかな脚力は、あっという間に彼女の姿を村の灯りから遠ざけていく。
しかし、背後から、力強い足音が追いかけてくる。洋介だった。彼の足音は、エリアーナの心の迷いを映すかのように、乱れることなく、しかし執拗に、すぐ後ろまで迫っていた。なぜ、追いかけてくるの。見知らぬ森の女を、どうして。
森の入り口、外界と聖域を隔てる巨大な夜樫(よるがし)の木の下で、エリアーナはとうとう足を止めた。これ以上、彼を森に引き入れてはならない。ここは、エルフの世界だ。人間が安易に踏み込めば、森の掟が、精霊たちが、彼を拒絶するだろう。
「待ってくれ!」
追いついた洋介は、肩で息をしながら、エリアーナの腕を掴んだ。その手に、強い力が込められている。触れられた腕から、まるで電気が走ったかのように、懐かしい感覚が全身を駆け巡った。ああ、この温もりだ。この、少し不器用で、でも力強い手の感触。百二十年間、夢に見続けた温もりだった。涙が、もう彼女の意思とは関係なく、後から後から溢れてくる。
「離してください。私は、あなたとは違う世界の者です。これ以上、関わるべきではない」
エリアーナは、彼に背を向けたまま、懇願するように言った。
「違う世界? だから何だと言うんだ」
洋介の声には、切実な響きがこもっていた。
「俺は、君のことを知りたい。君と初めて会った気がしないんだ。さっき、窓の外に君を見つけた時、まるで、ずっと探していた誰かに、やっと会えたような⋯⋯そんな気がした。君は、一体誰なんだ? なぜ、そんなに悲しい顔で、泣いているんだ?」
洋介の真っ直ぐな言葉が、エリアーナの最後の砦を打ち砕いた。彼は、エリアーナを回り込み、その泣き顔を覗き込んだ。その瞳は、昔と何も変わっていなかった。いつだって、彼はこうだった。実直で、自分の気持ちに正直で、そして、少しだけ不器用で、でも誰よりも優しかった。
「⋯⋯エリアーナ」
自分の名前を告げた瞬間、エリアーナは、後悔した。名前という楔を、打ってしまった。もう、後戻りはできない。彼との間に、細く、しかし確かな繋がりが、生まれてしまった。
「エリアーナ⋯⋯。美しい響きだ」
洋介は、その名前を確かめるように、ゆっくりと繰り返した。
「俺は洋介。この村で、家を造っている」
彼は、そう言って、戸惑いながらも、優しく微笑んだ。その笑顔は、かつて小田春音が、世界で一番好きだった笑顔そのものだった。エリアーナの感情は、ついに限界を超えた。百二十年分の孤独と、再会の喜びと、そして未来への絶望が、一つの巨大な奔流となって、彼女の口から溢れ出した。
「洋介⋯⋯! 会いたかった⋯⋯! ずっと、ずっと、あなたに会いたかった⋯⋯!」
エリアーナは、彼の胸に全ての重さを預けるように飛び込んでいた。洋介は突然のことに戸惑い、一瞬その体を硬直させたが、やがて、泣きじゃくる彼女の銀色の髪を、その背中を、まるで壊れ物を扱うかのように、優しく、優しく撫でていた。
その夜、二人は森の境界で夜が明けるまで語り合った。月が西に傾き、東の空が白み始めるまで二人の言葉が尽きることはなかった。エリアーナは、自分のことを全て話した。
小田春音として生きた二十数年の人生。出版社で働き、物語を愛していたこと。洋介と出会い、恋に落ちたこと。彼の設計する空間が、どれほど好きだったか。プロポーズされた日の舞い散る桜のこと。そして、結婚式の前日にブーケを抱えたまま、車に轢かれて死んでしまったこと。
次に目覚めた時、エルフのエリアーナとして、この忘れられた森に転生していたこと。そして、百二十年もの間、ただひたすらに彼を想い続けてきたこと。
洋介は時折、信じられないというように首を振りながらも、黙ってエリアーナの話を聞いていた。彼の表情は驚きと混乱、そして深い悲しみの間で目まぐるしく変わっていった。常識的に考えれば、到底受け入れられる話ではない。狂人の戯言だと思われても仕方がなかった。
だが、彼の魂は、彼女の言葉の一つ一つが真実であると告げていた。
「⋯⋯信じられない。俺の知っている世界では、ありえない話だ。だが⋯⋯」
洋介は言葉を選びながら、ゆっくりと続けた。
「だが、君の話は不思議とすんなりと心に入ってくる。君と初めて会った時から、ずっと感じていたんだ。この胸の奥がざわつくような、懐かしいような、切ないような、特別な感情の正体が今、分かった気がする」
彼は、エリアーナの冷たくなった手を自分の大きな両手でそっと包み込んだ。
「春音⋯⋯。そうだったのか。君は春音だったのか⋯⋯」
洋介の緑色の瞳から、大粒の涙が静かに流れ落ちた。それは、前世の記憶が蘇ったからではない。彼の中で、ずっと燻っていた正体不明の喪失感の理由を、今、理解したからだ。彼の魂はずっと彼女を探し続けていたのだ。
「ごめん⋯⋯ごめん、春音。思い出してやれなくて。一人で、百年も⋯⋯」
二人は、百二十年の時を超えて、ようやくお互いを認識し、抱きしめ合った。森の木々が、夜明け前の風にざわめき、二人の再会を祝福し、そして同時に、これから訪れるであろう過酷な運命を、予言しているかのようだった。
その喜びも束の間、二人の間には、あまりにも大きく、そして冷酷な壁が、改めて立ちはだかっていた。
エルフと人間。その絶望的なまでの、寿命の差。
再会を果たした日から、二人は、人目を忍んで会うようになった。昼間は、洋介は村の建築士として、エリアーナは森の癒し手として、それぞれの時間を生きる。そして、月が昇り、世界が眠りにつく頃、洋介は村を抜け出し、森の奥深くへと向かう。エリアーナは、森の入り口で彼を迎え、二人だけの聖域へと誘うのだ。
その場所は森のさらに奥深く、月光だけが差し込む小さな泉のほとりだった。泉の水は地中から湧き出る際に魔力を帯びた鉱石の層を通るため、まるで星屑を溶かし込んだかのようにきらきらと輝いていた。周囲には夜光苔が自生し、青白い幻想的な光を放っている。そこは人間はもちろん、ほとんどのエルフさえ足を踏み入れない、二人だけの秘密の場所だった。
二人は、そこで、失われた時間を取り戻すかのように語り合った。
エリアーナは洋介に、エルフの森の理(ことわり)を教えた。風の言葉の聞き分け方、精霊との対話の作法、傷を癒す魔法の初歩。彼女が泉の水を手にすくうと水は金色の光を放ち、その光に触れた夜光苔はより一層強く輝いた。
「すごい⋯⋯。魔法、か。本当にあるんだな」
洋介は、子供のように目を輝かせた。彼の世界は、合理性と物理法則で成り立っていた。その彼が、今、目の前で、科学では説明できない奇跡を目の当たりにしている。
一方、洋介は、エリアーナに人間の村の発展を語った。新しく計画している水路の設計、村人たちの間の些細な揉め事、そして、建築家として、いつかこの国の王都に誰もが見上げるような美しい建物を建てたいという夢。
「人間の世界は、目まぐるしく変わる。俺たちがこの村に来て、まだ数年だが景色は全く変わってしまった。だが、それが生きているという実感なんだ」
エリアーナは彼の話を聞くのが好きだった。彼の語る人間たちの営みは、停滞した森の時間にはない、力強い生命力に満ちていた。しかし同時に、その話を聞くたびに彼女の胸は締め付けられた。彼の言う「数年」は、彼女にとっては瞬きのような時間でしかない。彼の語る「未来」は、彼女の永遠の時間の中では、あまりにも、あまりにも短い。
幸せな時間の中で、エリアーナの心は常に冷たい不安に苛まれていた。
洋介の目尻に、以前はなかった細い笑いジワが増えていることに気づくたび、心臓が冷たくなる。日に焼けた彼の腕に新しい傷が刻まれているのを見るたび、彼の命が有限であることを、まざまざと見せつけられるようだった。彼の明るい茶色の髪に、月光を浴びてきらりと光る、一本の白いものを見つけてしまった夜は一睡もできなかった。
それはまるで、美しい砂時計の砂が、確実に落ちていくのを、なすすべなく見つめているような、残酷な時間だった。
一方、洋介もまた、エリアーナの変わらない姿に、焦りと、言いようのない劣等感のようなものを感じ始めていた。彼女は、百二十年前の「春音」の話をする時も、今、目の前で魔法を見せる時も、寸分違わぬ姿で、そこにいる。その透き通るような白い肌も、銀色に輝く髪も、若々しいまま、時が止まっている。
自分だけが彼女の横で、確実に歳をとり、老いていく。いつか、彼女の前で醜く老いさらばえてしまう日が来るのだ。その恐怖が、じわじわと洋介の心を蝕んでいった。彼は、彼女が自分を置いていくのではなく、自分が彼女についていけなくなることを恐れていた。
愛し合っているのに、お互いを想えば想うほど二人の間にある「時間」という名の深い溝は、よりくっきりと、その輪郭を現していく。そして、その溝は少しずつ、二人の間にすれ違いを生み出していった。
エリアーナは、洋介の体のことを心配するあまり、つい、母親のような小言を言ってしまうようになった。
「洋介、また夜更かしをしたの? 目の下に、隈ができているわ。あまり無理をしてはだめ。人間の体は、エルフと違って、脆いのだから」
「大丈夫だよ、春音。これくらい、どうってことない」
洋介は、笑って答えながらも、その声には、微かな苛立ちが混じっていた。エリアーナの気遣いが、自分の老いや、人間としての弱さを指摘されているようで、辛かったのだ。「エルフと違って」という言葉が、彼と彼女の間に引かれた、越えられない線を、嫌でも意識させた。
ある夜、エリアーナは、昔話をするように、無邪気に言った。
「この泉のほとりの夜光苔はね、私が生まれた頃から、ずっとこうして輝いているのよ。百二十年前も、きっと、この半分くらいの大きさだったかしら」
その言葉に、洋介は、何も答えられなかった。彼女が語る「百二十年前」という過去に、自分は存在しない。彼女の長い人生の、ほんの入り口に、自分は今、立っているに過ぎない。その事実が、彼に、深い疎外感を抱かせた。
二人の会話は、知らず知らずのうちにお互いを傷つける地雷を内包し始めていた。
そんな危ういバランスの上で成り立っていた二人の関係に、決定的な亀裂を入れる出来事が起こる。
村ができて五年目の収穫祭の季節がやってきた。村中が活気と喜びに満ち溢れる、一年で最も大きな祭りだ。洋介はエリアーナを、その祭りに誘った。
泉のほとりで、彼は、少し緊張した面持ちで切り出した。
「エリアーナ、今度の収穫祭に、一緒に来ないか? 村の皆に、君を紹介したいんだ。俺の、大切な人だって」
それは、洋介なりの、大きな一歩だった。いつまでも、こうして夜の森で、隠れるように会っている関係を、終わらせたかった。彼女を、自分の生きる、光の当たる場所へと、迎え入れたかったのだ。
しかし、エリアーナは、悲しそうな顔で、静かに首を横に振った。
「ごめんなさい、洋介。私は行けないわ」
「どうしてだ!?」
「エルフが人間の村の祭りに現れたら、どんな騒ぎになるか分かるでしょう? 皆、私を好奇の目や恐怖の目で見るだけよ。あなたの立場も悪くなってしまうわ」
「そんなことはない! 俺が皆に、ちゃんと説明する! それに俺は、君を誰かに見られて困るような存在だなんて思ったことは一度もない!」
「無理よ、洋介」
エリアーナの声は、頑なだった。
「私たちは住む世界が違うの。あなたにも迷惑がかかるわ。お願い、分かって」
彼女の言葉は洋介の心を深く傷つけた。「住む世界が違う」。それは、彼が最も聞きたくない言葉だった。エリアーナは洋介を拒絶しているのではなかった。彼を、彼の築き上げてきた人間社会を守るために、自ら一歩を引いたのだ。そして何より、人々の輪の中でリリアと共に笑う彼の姿を間近で見ることに、耐えられそうになかった。それは彼女の、あまりにも悲しい自己防衛だった。
しかし、その想いは洋介には届かなかった。彼にはそれが、自分との間に明確な壁を作る、冷たい拒絶の言葉にしか聞こえなかったのだ。
「⋯⋯そうか。分かったよ」
洋介は、それ以上何も言わなかった。ただ、深く傷ついたような、寂しそうな目をして、踵を返し、一人、村へと帰っていった。
結局、洋介は、一人で祭りに参加した。
祭りの夜、村の中央広場には大きな焚き火が焚かれ、人々はその周りで、歌い、踊り、収穫の恵みに感謝していた。洋介は、その輪の中にいたが、心から笑うことはできなかった。彼の心は、森の奥深くで、一人、この喧騒を聞いているであろう、エリアーナの元にあった。
そんな彼の元に、リリアが木の実の酒が入った杯を持ってやってきた。
「洋介、元気ないわね。何か悩み事?」
彼女は何も聞かず、ただ彼の隣に座り、優しく微笑んだ。村人たちは、そんな二人を見て「お似合いの二人だ」「村の未来は、あの二人に任せれば安心だ」と、口々に囃し立てた。誰もが若きリーダーである洋介と、村長の娘であるリリアが結ばれることを望んでいた。
その全ての光景を。
祭りの灯りが届かない、遠く離れた丘の上の、木の陰から。
エリアーナは、ただ一人、黙って見つめていた。胸が張り裂けそうに痛い。
洋介の隣にいるべきなのは自分なのに。彼が本当に愛しているのは自分なのに。しかし、自分には、あの光の輪の中に入っていく資格がない。彼に、人間の幸福を与えてあげることはできない。
祭りの喧騒、人々の笑い声、陽気な音楽。その全てが自分だけを拒絶する、高い、高い壁のように感じられた。リリアの太陽のような笑顔が、自分の心を容赦なく抉っていく。嫉妬と、自己嫌悪と、そしてどうしようもない悲しみが、彼女の中で黒い渦を巻いていた。
祭りの後、洋介はエリアーナの元を訪れなかった。エリアーナもまた、彼に会いに行くことができなかった。会えば彼を傷つけてしまう。会えば自分が壊れてしまう。
二人の心の距離は物理的な距離以上に遠く、そして、絶望的に離れてしまったかのようだった。
森の奥の泉は、以前と変わらず神秘的な光を放っていたが、そこに、二人の姿が映し出されることはもうなかった。
「⋯⋯森の者です」
エリアーナは、喉の奥からやっとの思いで言葉を絞り出した。声が震えないように、全身の神経を集中させる。
「村の様子が気になって、少し見に来ただけ。⋯⋯お騒がせしました」
そう言って、彼女は身を翻した。一刻も早く、この場から逃げ出したかった。彼の瞳に見つめられているだけで、築き上げてきた百二十年分の理性が、砂の城のように崩れ落ちてしまいそうだったからだ。追いかけてくるな、と心の中で絶叫しながら、彼女は闇の中へと駆け出した。エルフのしなやかな脚力は、あっという間に彼女の姿を村の灯りから遠ざけていく。
しかし、背後から、力強い足音が追いかけてくる。洋介だった。彼の足音は、エリアーナの心の迷いを映すかのように、乱れることなく、しかし執拗に、すぐ後ろまで迫っていた。なぜ、追いかけてくるの。見知らぬ森の女を、どうして。
森の入り口、外界と聖域を隔てる巨大な夜樫(よるがし)の木の下で、エリアーナはとうとう足を止めた。これ以上、彼を森に引き入れてはならない。ここは、エルフの世界だ。人間が安易に踏み込めば、森の掟が、精霊たちが、彼を拒絶するだろう。
「待ってくれ!」
追いついた洋介は、肩で息をしながら、エリアーナの腕を掴んだ。その手に、強い力が込められている。触れられた腕から、まるで電気が走ったかのように、懐かしい感覚が全身を駆け巡った。ああ、この温もりだ。この、少し不器用で、でも力強い手の感触。百二十年間、夢に見続けた温もりだった。涙が、もう彼女の意思とは関係なく、後から後から溢れてくる。
「離してください。私は、あなたとは違う世界の者です。これ以上、関わるべきではない」
エリアーナは、彼に背を向けたまま、懇願するように言った。
「違う世界? だから何だと言うんだ」
洋介の声には、切実な響きがこもっていた。
「俺は、君のことを知りたい。君と初めて会った気がしないんだ。さっき、窓の外に君を見つけた時、まるで、ずっと探していた誰かに、やっと会えたような⋯⋯そんな気がした。君は、一体誰なんだ? なぜ、そんなに悲しい顔で、泣いているんだ?」
洋介の真っ直ぐな言葉が、エリアーナの最後の砦を打ち砕いた。彼は、エリアーナを回り込み、その泣き顔を覗き込んだ。その瞳は、昔と何も変わっていなかった。いつだって、彼はこうだった。実直で、自分の気持ちに正直で、そして、少しだけ不器用で、でも誰よりも優しかった。
「⋯⋯エリアーナ」
自分の名前を告げた瞬間、エリアーナは、後悔した。名前という楔を、打ってしまった。もう、後戻りはできない。彼との間に、細く、しかし確かな繋がりが、生まれてしまった。
「エリアーナ⋯⋯。美しい響きだ」
洋介は、その名前を確かめるように、ゆっくりと繰り返した。
「俺は洋介。この村で、家を造っている」
彼は、そう言って、戸惑いながらも、優しく微笑んだ。その笑顔は、かつて小田春音が、世界で一番好きだった笑顔そのものだった。エリアーナの感情は、ついに限界を超えた。百二十年分の孤独と、再会の喜びと、そして未来への絶望が、一つの巨大な奔流となって、彼女の口から溢れ出した。
「洋介⋯⋯! 会いたかった⋯⋯! ずっと、ずっと、あなたに会いたかった⋯⋯!」
エリアーナは、彼の胸に全ての重さを預けるように飛び込んでいた。洋介は突然のことに戸惑い、一瞬その体を硬直させたが、やがて、泣きじゃくる彼女の銀色の髪を、その背中を、まるで壊れ物を扱うかのように、優しく、優しく撫でていた。
その夜、二人は森の境界で夜が明けるまで語り合った。月が西に傾き、東の空が白み始めるまで二人の言葉が尽きることはなかった。エリアーナは、自分のことを全て話した。
小田春音として生きた二十数年の人生。出版社で働き、物語を愛していたこと。洋介と出会い、恋に落ちたこと。彼の設計する空間が、どれほど好きだったか。プロポーズされた日の舞い散る桜のこと。そして、結婚式の前日にブーケを抱えたまま、車に轢かれて死んでしまったこと。
次に目覚めた時、エルフのエリアーナとして、この忘れられた森に転生していたこと。そして、百二十年もの間、ただひたすらに彼を想い続けてきたこと。
洋介は時折、信じられないというように首を振りながらも、黙ってエリアーナの話を聞いていた。彼の表情は驚きと混乱、そして深い悲しみの間で目まぐるしく変わっていった。常識的に考えれば、到底受け入れられる話ではない。狂人の戯言だと思われても仕方がなかった。
だが、彼の魂は、彼女の言葉の一つ一つが真実であると告げていた。
「⋯⋯信じられない。俺の知っている世界では、ありえない話だ。だが⋯⋯」
洋介は言葉を選びながら、ゆっくりと続けた。
「だが、君の話は不思議とすんなりと心に入ってくる。君と初めて会った時から、ずっと感じていたんだ。この胸の奥がざわつくような、懐かしいような、切ないような、特別な感情の正体が今、分かった気がする」
彼は、エリアーナの冷たくなった手を自分の大きな両手でそっと包み込んだ。
「春音⋯⋯。そうだったのか。君は春音だったのか⋯⋯」
洋介の緑色の瞳から、大粒の涙が静かに流れ落ちた。それは、前世の記憶が蘇ったからではない。彼の中で、ずっと燻っていた正体不明の喪失感の理由を、今、理解したからだ。彼の魂はずっと彼女を探し続けていたのだ。
「ごめん⋯⋯ごめん、春音。思い出してやれなくて。一人で、百年も⋯⋯」
二人は、百二十年の時を超えて、ようやくお互いを認識し、抱きしめ合った。森の木々が、夜明け前の風にざわめき、二人の再会を祝福し、そして同時に、これから訪れるであろう過酷な運命を、予言しているかのようだった。
その喜びも束の間、二人の間には、あまりにも大きく、そして冷酷な壁が、改めて立ちはだかっていた。
エルフと人間。その絶望的なまでの、寿命の差。
再会を果たした日から、二人は、人目を忍んで会うようになった。昼間は、洋介は村の建築士として、エリアーナは森の癒し手として、それぞれの時間を生きる。そして、月が昇り、世界が眠りにつく頃、洋介は村を抜け出し、森の奥深くへと向かう。エリアーナは、森の入り口で彼を迎え、二人だけの聖域へと誘うのだ。
その場所は森のさらに奥深く、月光だけが差し込む小さな泉のほとりだった。泉の水は地中から湧き出る際に魔力を帯びた鉱石の層を通るため、まるで星屑を溶かし込んだかのようにきらきらと輝いていた。周囲には夜光苔が自生し、青白い幻想的な光を放っている。そこは人間はもちろん、ほとんどのエルフさえ足を踏み入れない、二人だけの秘密の場所だった。
二人は、そこで、失われた時間を取り戻すかのように語り合った。
エリアーナは洋介に、エルフの森の理(ことわり)を教えた。風の言葉の聞き分け方、精霊との対話の作法、傷を癒す魔法の初歩。彼女が泉の水を手にすくうと水は金色の光を放ち、その光に触れた夜光苔はより一層強く輝いた。
「すごい⋯⋯。魔法、か。本当にあるんだな」
洋介は、子供のように目を輝かせた。彼の世界は、合理性と物理法則で成り立っていた。その彼が、今、目の前で、科学では説明できない奇跡を目の当たりにしている。
一方、洋介は、エリアーナに人間の村の発展を語った。新しく計画している水路の設計、村人たちの間の些細な揉め事、そして、建築家として、いつかこの国の王都に誰もが見上げるような美しい建物を建てたいという夢。
「人間の世界は、目まぐるしく変わる。俺たちがこの村に来て、まだ数年だが景色は全く変わってしまった。だが、それが生きているという実感なんだ」
エリアーナは彼の話を聞くのが好きだった。彼の語る人間たちの営みは、停滞した森の時間にはない、力強い生命力に満ちていた。しかし同時に、その話を聞くたびに彼女の胸は締め付けられた。彼の言う「数年」は、彼女にとっては瞬きのような時間でしかない。彼の語る「未来」は、彼女の永遠の時間の中では、あまりにも、あまりにも短い。
幸せな時間の中で、エリアーナの心は常に冷たい不安に苛まれていた。
洋介の目尻に、以前はなかった細い笑いジワが増えていることに気づくたび、心臓が冷たくなる。日に焼けた彼の腕に新しい傷が刻まれているのを見るたび、彼の命が有限であることを、まざまざと見せつけられるようだった。彼の明るい茶色の髪に、月光を浴びてきらりと光る、一本の白いものを見つけてしまった夜は一睡もできなかった。
それはまるで、美しい砂時計の砂が、確実に落ちていくのを、なすすべなく見つめているような、残酷な時間だった。
一方、洋介もまた、エリアーナの変わらない姿に、焦りと、言いようのない劣等感のようなものを感じ始めていた。彼女は、百二十年前の「春音」の話をする時も、今、目の前で魔法を見せる時も、寸分違わぬ姿で、そこにいる。その透き通るような白い肌も、銀色に輝く髪も、若々しいまま、時が止まっている。
自分だけが彼女の横で、確実に歳をとり、老いていく。いつか、彼女の前で醜く老いさらばえてしまう日が来るのだ。その恐怖が、じわじわと洋介の心を蝕んでいった。彼は、彼女が自分を置いていくのではなく、自分が彼女についていけなくなることを恐れていた。
愛し合っているのに、お互いを想えば想うほど二人の間にある「時間」という名の深い溝は、よりくっきりと、その輪郭を現していく。そして、その溝は少しずつ、二人の間にすれ違いを生み出していった。
エリアーナは、洋介の体のことを心配するあまり、つい、母親のような小言を言ってしまうようになった。
「洋介、また夜更かしをしたの? 目の下に、隈ができているわ。あまり無理をしてはだめ。人間の体は、エルフと違って、脆いのだから」
「大丈夫だよ、春音。これくらい、どうってことない」
洋介は、笑って答えながらも、その声には、微かな苛立ちが混じっていた。エリアーナの気遣いが、自分の老いや、人間としての弱さを指摘されているようで、辛かったのだ。「エルフと違って」という言葉が、彼と彼女の間に引かれた、越えられない線を、嫌でも意識させた。
ある夜、エリアーナは、昔話をするように、無邪気に言った。
「この泉のほとりの夜光苔はね、私が生まれた頃から、ずっとこうして輝いているのよ。百二十年前も、きっと、この半分くらいの大きさだったかしら」
その言葉に、洋介は、何も答えられなかった。彼女が語る「百二十年前」という過去に、自分は存在しない。彼女の長い人生の、ほんの入り口に、自分は今、立っているに過ぎない。その事実が、彼に、深い疎外感を抱かせた。
二人の会話は、知らず知らずのうちにお互いを傷つける地雷を内包し始めていた。
そんな危ういバランスの上で成り立っていた二人の関係に、決定的な亀裂を入れる出来事が起こる。
村ができて五年目の収穫祭の季節がやってきた。村中が活気と喜びに満ち溢れる、一年で最も大きな祭りだ。洋介はエリアーナを、その祭りに誘った。
泉のほとりで、彼は、少し緊張した面持ちで切り出した。
「エリアーナ、今度の収穫祭に、一緒に来ないか? 村の皆に、君を紹介したいんだ。俺の、大切な人だって」
それは、洋介なりの、大きな一歩だった。いつまでも、こうして夜の森で、隠れるように会っている関係を、終わらせたかった。彼女を、自分の生きる、光の当たる場所へと、迎え入れたかったのだ。
しかし、エリアーナは、悲しそうな顔で、静かに首を横に振った。
「ごめんなさい、洋介。私は行けないわ」
「どうしてだ!?」
「エルフが人間の村の祭りに現れたら、どんな騒ぎになるか分かるでしょう? 皆、私を好奇の目や恐怖の目で見るだけよ。あなたの立場も悪くなってしまうわ」
「そんなことはない! 俺が皆に、ちゃんと説明する! それに俺は、君を誰かに見られて困るような存在だなんて思ったことは一度もない!」
「無理よ、洋介」
エリアーナの声は、頑なだった。
「私たちは住む世界が違うの。あなたにも迷惑がかかるわ。お願い、分かって」
彼女の言葉は洋介の心を深く傷つけた。「住む世界が違う」。それは、彼が最も聞きたくない言葉だった。エリアーナは洋介を拒絶しているのではなかった。彼を、彼の築き上げてきた人間社会を守るために、自ら一歩を引いたのだ。そして何より、人々の輪の中でリリアと共に笑う彼の姿を間近で見ることに、耐えられそうになかった。それは彼女の、あまりにも悲しい自己防衛だった。
しかし、その想いは洋介には届かなかった。彼にはそれが、自分との間に明確な壁を作る、冷たい拒絶の言葉にしか聞こえなかったのだ。
「⋯⋯そうか。分かったよ」
洋介は、それ以上何も言わなかった。ただ、深く傷ついたような、寂しそうな目をして、踵を返し、一人、村へと帰っていった。
結局、洋介は、一人で祭りに参加した。
祭りの夜、村の中央広場には大きな焚き火が焚かれ、人々はその周りで、歌い、踊り、収穫の恵みに感謝していた。洋介は、その輪の中にいたが、心から笑うことはできなかった。彼の心は、森の奥深くで、一人、この喧騒を聞いているであろう、エリアーナの元にあった。
そんな彼の元に、リリアが木の実の酒が入った杯を持ってやってきた。
「洋介、元気ないわね。何か悩み事?」
彼女は何も聞かず、ただ彼の隣に座り、優しく微笑んだ。村人たちは、そんな二人を見て「お似合いの二人だ」「村の未来は、あの二人に任せれば安心だ」と、口々に囃し立てた。誰もが若きリーダーである洋介と、村長の娘であるリリアが結ばれることを望んでいた。
その全ての光景を。
祭りの灯りが届かない、遠く離れた丘の上の、木の陰から。
エリアーナは、ただ一人、黙って見つめていた。胸が張り裂けそうに痛い。
洋介の隣にいるべきなのは自分なのに。彼が本当に愛しているのは自分なのに。しかし、自分には、あの光の輪の中に入っていく資格がない。彼に、人間の幸福を与えてあげることはできない。
祭りの喧騒、人々の笑い声、陽気な音楽。その全てが自分だけを拒絶する、高い、高い壁のように感じられた。リリアの太陽のような笑顔が、自分の心を容赦なく抉っていく。嫉妬と、自己嫌悪と、そしてどうしようもない悲しみが、彼女の中で黒い渦を巻いていた。
祭りの後、洋介はエリアーナの元を訪れなかった。エリアーナもまた、彼に会いに行くことができなかった。会えば彼を傷つけてしまう。会えば自分が壊れてしまう。
二人の心の距離は物理的な距離以上に遠く、そして、絶望的に離れてしまったかのようだった。
森の奥の泉は、以前と変わらず神秘的な光を放っていたが、そこに、二人の姿が映し出されることはもうなかった。
第四章:心の葛藤、埋まらない溝
収穫祭の夜、二人の間に生まれた亀裂は時が経つほどに深く、そして広くなっていった。洋介がエリアーナの元を訪れなくなってから、一月(ひとつき)の時が流れた。人間にとっては三十日という具体的な日数だが、エリアーナにとっては、まるで永遠にも感じられる、長く、そして空虚な時間だった。彼女の日課は、変わらず森の境界から人間の村を眺めることだった。しかし、その目的は以前とは全く異なっていた。かつては、彼の姿を一目見るだけで満たされた心が、今は、彼の姿を探せば探すほど渇きと痛みを増していく。村の家々から立ち上る煙、畑を耕す人々の小さな影、子供たちの甲高い笑い声。その全てが自分が属することのできない幸せな世界の象徴に見えた。そして、その世界の中心にいるはずの洋介の姿を彼女は見つけることができなかった。
彼が自分を避けていることは、痛いほど分かっていた。祭りの夜に見せた、あの深く傷ついた瞳。自分の言葉が、ナイフのように彼を切り裂いたのだ。あの時、どうして、「一緒に行きたい」と素直に言えなかったのだろう。どうして、「あなたの隣にいたい」と、ただその一言が、言えなかったのだろう。エルフとしての矜持か、それとも、リリアへの嫉妬心を彼に見透かされることへの恐怖か。今となっては、どちらも言い訳に過ぎなかった。
自分のせいだ。私が、彼を傷つけた。
彼を愛しているのに、その愛し方が分からない。
エルフとしての長い時間が、私から、人間らしい素直な感情を奪ってしまったのだろうか。それとも、「小田春音」であった頃から、私は、臆病で、不器用な人間だったのだろうか。
自問自答は、答えのない迷宮の中を、ただひたすらに彷徨うだけだった。泉のほとりに一人佇み、水面に映る自分の顔を見つめる。そこには、何の感情も浮かべていない、人形のように美しいエルフの顔があるだけだった。その無表情さが、彼女をさらに孤独にした。
一方、洋介もまた、苦悩の日々を送っていた。彼の心は、真っ二つに引き裂かれていた。
昼間、彼は村のリーダーとして、建築士として、多忙な日々を送っていた。新しい家の建設、水路の補修、村人同士の諍いの仲裁。やるべきことは、山のようにあった。村人たちの信頼と期待を一身に背負い、彼は、その責任から逃げることは許されなかった。そして、そんな彼を、リリアが献身的に支えてくれていた。
彼女は、洋介の心の内に、エリアーナという存在がいることを、薄々感じ取っているようだった。しかし、決してそれを問いただすことはせず、ただ、以前にも増して明るく、甲斐甲斐しく、彼の世話を焼いた。彼女の太陽のような明るさは、エリアーナを想って沈みがちになる洋介の心を、何度も、何度も救ってくれた。
「洋介、また難しい顔をして。眉間に、深い谷ができてるわよ」
リリアは、そう言って、悪戯っぽく彼の眉間を指でつつく。その屈託のない優しさに触れるたび、洋介の心は、罪悪感でいっぱいになった。リリアと結婚すれば、自分は、人並みの幸せを手に入れることができるだろう。温かい家庭を築き、子供を育て、孫の顔を見て、穏やかに老いていく。それが、人間としての、自然で、正しい生き方なのだ。村の誰もが、それを望んでいる。
しかし、夜が来て、一人きりで机に向かうと、彼の心は、森の奥深くへと飛んでいった。
エリアーナに会いたい。狂おしいほどに、会いたい。
彼女の銀色の髪に触れたい。透き通るような声が聞きたい。そして、あの憂いを帯びた美しい瞳に、自分だけを映してほしい。
しかし、会えば、また彼女を傷つけてしまうかもしれない。「住む世界が違う」。彼女が放った言葉は、呪いのように、彼の心にまとわりついて離れない。彼女の言う通りなのだ。自分たちは、決して交わることのない、二つの平行線の上を歩いている。その事実が、重く、重く、洋介の心にのしかかっていた。
彼は、エリアーナを愛していた。しかし、同時に、リリアの優しさにも、確実に惹かれていた。二人の女性の間で、彼の心は、振り子のように揺れ動き、安らぐ場所を見つけられずにいた。
そんな、膠着した状況を、打ち破ったのは、予期せぬ、そして残酷な出来事だった。
秋の収穫も終わり、村に冬の気配が忍び寄り始めた頃。村で、原因不明の病が流行り始めたのだ。
最初は、軽い咳や微熱といった、ありふれた風邪のような症状だった。誰もが、すぐに治るだろうと高を括っていた。しかし、病は人々の楽観を嘲笑うかのように、その牙を剥いた。咳は次第に激しくなり、呼吸をするたびに喉からヒューヒューという苦しげな音が漏れるようになった。高熱に浮かされ、人々は悪夢にうなされ始めた。そして、発症から数日後には、呼吸が完全に困難になり、青白い顔で、息絶えていく者が、ぽつり、ぽつりと出始めた。
村に一つしかない、老医師が営む小さな診療所には、対応しきれないほどの患者が押し寄せた。薬草は、瞬く間に底をつき、なすすべもなく、苦しむ家族を見守ることしかできない人々。村は、これまで経験したことのない、静かなパニックに陥った。笑い声は消え、人々の顔からは表情が失われ、死の匂いが冷たい冬の風に乗って、村の隅々まで漂っていた。
そして、その病の魔の手は、リリアにも、容赦なく襲いかかった。
最初は、軽い咳だった。洋介は、彼女に、無理せず休むように言った。しかし、彼女は、「大丈夫よ、これくらい」と、気丈に笑い、病人の看病を続けた。だが、数日後、彼女は、高熱を出して倒れた。
洋介は、リリアの家で彼女の看病にあたった。真っ赤な顔で、荒い息を繰り返すリリア。その額に乗せた濡れ布は、すぐに熱くなってしまう。時折、うわ言で洋介の名前を呼ぶ。その苦しそうな姿を見ていると、洋介は、自分の無力さに絶望的な気持ちになった。
建築士である自分には、病を治す力はない。家は建てられても、人の命を救うことはできない。ただ、彼女の熱い手を握り、神に祈ることしかできないのだ。
その時、洋介の脳裏に、鮮やかに、ある光景が蘇った。
森の奥深く、月光が差し込む泉のほとり。エリアーナが、泉の水を手にすくうと水は金色の癒しの光を放った。あの光ならば。彼女の、あの不思議な力ならば。
リリアを、村の人々を救えるかもしれない。
その考えは、一筋の光明のように彼の絶望を照らした。しかし同時に、深い葛藤が彼を苛んだ。
エリアーナに助けを求めること。それは彼女を危険に晒すことになるかもしれない。人間たちはエルフという存在に対して、畏敬の念と同時に得体の知れないものへの恐怖心も抱いている。もし、彼女の力が村人たちに、悪魔の業として誤解されてしまったら? 彼女が、迫害の対象になってしまうかもしれない。
そして何よりも洋介自身の、男としてのプライドがそれを許さなかった。
祭りの夜、彼女に事実上拒絶された身だ。自分との間に壁を作り、会うことすら避けている彼女に今更どの面下げて助けを求めろと言うのか。しかも、助けてほしいのは恋敵であるはずのリリアなのだ。それはあまりにも身勝手で、虫のいい話ではないか。
プライドが彼に森へ行くことを躊躇させた。
しかし、リリアの容態は刻一刻と悪化していく。呼吸はますます浅くなり、意識も朦朧とし始めている。彼女の弱々しい呼吸を聞きながら、洋介の心の中で天秤が大きく揺れ動いていた。
自分のちっぽけなプライド。それとリリアのかけがえのない命。
比べるまでもない。
洋介は、歯を食いしばり、ついに決断した。プライドなど、どうでもいい。今、一番大切なのはリリアの命だ。彼女を失うことの方が、何千倍も、何万倍も、怖い。
洋介は、リリアの父親である村長に、後を託すと、家を飛び出した。夜の闇に紛れて、彼は、森へと走った。凍てつくような冬の風が、彼の頬を容赦なく打ちつける。
森の入り口に立ち、彼は一瞬ためらった。エリアーナに拒絶されたらどうしよう。罵られても仕方がない。それでも行くしかないのだ。
彼は、かつて、エリアーナと何度も歩いた道を、記憶だけを頼りに進んでいった。二人だけの聖域であった、あの泉のほとりへ。しかし、そこに彼女の姿はなかった。月光に照らされた泉が星屑を散りばめたように、静かに輝いているだけだった。
「エリアーナ!」
洋介は、必死に叫んだ。
「エリアーナ、どこだ! 頼む、出てきてくれ! 話があるんだ!」
彼の声は森の静寂に、虚しく吸い込まれていく。木霊すら返ってこない。彼女は、もう、この場所にさえ来ていないのだろうか。自分のことを完全に忘れようとしているのだろうか。絶望が彼の心を再び支配しようとした。
諦めかけて、その場に崩れ落ちそうになった、その時。
背後の巨大な夜樫の木の陰から、鈴を転がすような、しかし、氷のように冷たい声が聞こえた。
「⋯⋯私に何か用ですか。人間のあなたが、このような森の奥深くまで」
振り返ると、そこにエリアーナが立っていた。
月光を背に受け、その輪郭は青白く光っている。その表情は、以前よりもさらに硬く、冷たく、まるで美しい氷の彫像のようだった。彼女の瞳には、何の感情も浮かんでいなかった。
「エリアーナ⋯⋯! よかった、会えて⋯⋯」
洋介は、安堵と切実な思いで、彼女に駆け寄ろうとした。しかし、彼女の冷たい視線が彼をその場に縫い付けた。
「頼む、助けてくれ!」
洋介は、たまらずその場に膝をついた。土下座をするように、深く頭を下げた。
「村で、病が流行っているんだ。皆、苦しんでいる。リリアも⋯⋯リリアも、今、死にかけている! 君の力で、彼女を、村を、救ってほしい! この通りだ、お願いだ!」
エリアーナは、そんな彼の姿を、無表情のまま、ただ、見下ろしていた。リリア、という名を聞いた瞬間も、彼女の表情は、ピクリとも動かなかった。
長い、長い、沈黙が、二人を支配した。聞こえるのは、風が木々を揺らす音と、洋介の、荒い息遣いだけだった。
やがて、エリアーナの赤い唇がゆっくりと開かれた。
「⋯⋯なぜ、私が?」
その声は、冬の泉の水のように、冷え冷えとしていた。
「あなたは、私ではなく、あの子を選んだはず。人間の女と、人間としての幸せを。それに、私は、人間を助ける義理など、ありません。彼らが、どうなろうと、私の知ったことではないわ」
エリアーナの刃物のように冷たい言葉が、洋介の心を、容赦なく抉る。分かっていた。そう言われることは、覚悟していた。しかし、実際に、彼女の口から、その言葉を聞くと、全身の血が、逆流するような思いだった。
それでも、彼は、諦めなかった。
「分かっている! 俺が君を傷つけたことは、分かっている! 俺が君を拒絶し、君に甘え、君を苦しめた! 全部、分かっているつもりだ! でも、頼む! このままでは、皆死んでしまうんだ! リリアだけじゃない、罪のない、大勢の人々が苦しんでいるんだ! 君は、治癒の力を持っているんだろう!? 苦しむ者を見捨てることができるのか! それでも君は、森の癒し手なのか!?」
洋介の魂からの悲痛な叫びだった。その言葉に、エリアーナの氷の仮面がわずかに揺らいだ。彼女の瞳の奥で、何かが激しく葛藤しているのが見えた。
彼女はエルフだ。森の理と共に生きる癒し手だ。苦しむ者を見捨ててはおけない。それは彼女の、エルフとしての本能であり、使命だった。
しかし、彼女の心の中では、人間としての「小田春音」の、黒い感情が、激しく渦巻いていた。
なぜ、私が?
なぜ、私が、あなたの恋敵を、助けなければならないの?
あなたが、私を捨てて、選んだ女を。彼女が死ねば、あなたは、私の元へ、戻ってくるかもしれないのに。
そんな、醜い考えが、鎌首をもたげる。エルフとしての使命感と、人間としての嫉妬心。聖と俗。二つの感情が、エリアーナの中で、激しく、激しく、ぶつかり合っていた。彼女は、唇を、血が滲むほど、強く、噛み締めた。
長い、息が詰まるような沈黙の後。
エリアーナは、全ての感情を、心の奥底に押し殺し、静かに、口を開いた。
「⋯⋯いいでしょう。ただし、条件があります」
その声には、もう、何の温度も、感じられなかった。
「私が、あなたの村人を救ったら、あなたは、二度と私の前に現れないで。私のことを、私の存在を、あなたの記憶から、綺麗さっぱり、消し去ってください」
それは、エリアーナが自分の心を、自らの手で殺して絞り出した、あまりにも、あまりにも、悲しい条件だった。彼を救うための唯一の方法が、彼との永遠の決別だった。
彼が自分を避けていることは、痛いほど分かっていた。祭りの夜に見せた、あの深く傷ついた瞳。自分の言葉が、ナイフのように彼を切り裂いたのだ。あの時、どうして、「一緒に行きたい」と素直に言えなかったのだろう。どうして、「あなたの隣にいたい」と、ただその一言が、言えなかったのだろう。エルフとしての矜持か、それとも、リリアへの嫉妬心を彼に見透かされることへの恐怖か。今となっては、どちらも言い訳に過ぎなかった。
自分のせいだ。私が、彼を傷つけた。
彼を愛しているのに、その愛し方が分からない。
エルフとしての長い時間が、私から、人間らしい素直な感情を奪ってしまったのだろうか。それとも、「小田春音」であった頃から、私は、臆病で、不器用な人間だったのだろうか。
自問自答は、答えのない迷宮の中を、ただひたすらに彷徨うだけだった。泉のほとりに一人佇み、水面に映る自分の顔を見つめる。そこには、何の感情も浮かべていない、人形のように美しいエルフの顔があるだけだった。その無表情さが、彼女をさらに孤独にした。
一方、洋介もまた、苦悩の日々を送っていた。彼の心は、真っ二つに引き裂かれていた。
昼間、彼は村のリーダーとして、建築士として、多忙な日々を送っていた。新しい家の建設、水路の補修、村人同士の諍いの仲裁。やるべきことは、山のようにあった。村人たちの信頼と期待を一身に背負い、彼は、その責任から逃げることは許されなかった。そして、そんな彼を、リリアが献身的に支えてくれていた。
彼女は、洋介の心の内に、エリアーナという存在がいることを、薄々感じ取っているようだった。しかし、決してそれを問いただすことはせず、ただ、以前にも増して明るく、甲斐甲斐しく、彼の世話を焼いた。彼女の太陽のような明るさは、エリアーナを想って沈みがちになる洋介の心を、何度も、何度も救ってくれた。
「洋介、また難しい顔をして。眉間に、深い谷ができてるわよ」
リリアは、そう言って、悪戯っぽく彼の眉間を指でつつく。その屈託のない優しさに触れるたび、洋介の心は、罪悪感でいっぱいになった。リリアと結婚すれば、自分は、人並みの幸せを手に入れることができるだろう。温かい家庭を築き、子供を育て、孫の顔を見て、穏やかに老いていく。それが、人間としての、自然で、正しい生き方なのだ。村の誰もが、それを望んでいる。
しかし、夜が来て、一人きりで机に向かうと、彼の心は、森の奥深くへと飛んでいった。
エリアーナに会いたい。狂おしいほどに、会いたい。
彼女の銀色の髪に触れたい。透き通るような声が聞きたい。そして、あの憂いを帯びた美しい瞳に、自分だけを映してほしい。
しかし、会えば、また彼女を傷つけてしまうかもしれない。「住む世界が違う」。彼女が放った言葉は、呪いのように、彼の心にまとわりついて離れない。彼女の言う通りなのだ。自分たちは、決して交わることのない、二つの平行線の上を歩いている。その事実が、重く、重く、洋介の心にのしかかっていた。
彼は、エリアーナを愛していた。しかし、同時に、リリアの優しさにも、確実に惹かれていた。二人の女性の間で、彼の心は、振り子のように揺れ動き、安らぐ場所を見つけられずにいた。
そんな、膠着した状況を、打ち破ったのは、予期せぬ、そして残酷な出来事だった。
秋の収穫も終わり、村に冬の気配が忍び寄り始めた頃。村で、原因不明の病が流行り始めたのだ。
最初は、軽い咳や微熱といった、ありふれた風邪のような症状だった。誰もが、すぐに治るだろうと高を括っていた。しかし、病は人々の楽観を嘲笑うかのように、その牙を剥いた。咳は次第に激しくなり、呼吸をするたびに喉からヒューヒューという苦しげな音が漏れるようになった。高熱に浮かされ、人々は悪夢にうなされ始めた。そして、発症から数日後には、呼吸が完全に困難になり、青白い顔で、息絶えていく者が、ぽつり、ぽつりと出始めた。
村に一つしかない、老医師が営む小さな診療所には、対応しきれないほどの患者が押し寄せた。薬草は、瞬く間に底をつき、なすすべもなく、苦しむ家族を見守ることしかできない人々。村は、これまで経験したことのない、静かなパニックに陥った。笑い声は消え、人々の顔からは表情が失われ、死の匂いが冷たい冬の風に乗って、村の隅々まで漂っていた。
そして、その病の魔の手は、リリアにも、容赦なく襲いかかった。
最初は、軽い咳だった。洋介は、彼女に、無理せず休むように言った。しかし、彼女は、「大丈夫よ、これくらい」と、気丈に笑い、病人の看病を続けた。だが、数日後、彼女は、高熱を出して倒れた。
洋介は、リリアの家で彼女の看病にあたった。真っ赤な顔で、荒い息を繰り返すリリア。その額に乗せた濡れ布は、すぐに熱くなってしまう。時折、うわ言で洋介の名前を呼ぶ。その苦しそうな姿を見ていると、洋介は、自分の無力さに絶望的な気持ちになった。
建築士である自分には、病を治す力はない。家は建てられても、人の命を救うことはできない。ただ、彼女の熱い手を握り、神に祈ることしかできないのだ。
その時、洋介の脳裏に、鮮やかに、ある光景が蘇った。
森の奥深く、月光が差し込む泉のほとり。エリアーナが、泉の水を手にすくうと水は金色の癒しの光を放った。あの光ならば。彼女の、あの不思議な力ならば。
リリアを、村の人々を救えるかもしれない。
その考えは、一筋の光明のように彼の絶望を照らした。しかし同時に、深い葛藤が彼を苛んだ。
エリアーナに助けを求めること。それは彼女を危険に晒すことになるかもしれない。人間たちはエルフという存在に対して、畏敬の念と同時に得体の知れないものへの恐怖心も抱いている。もし、彼女の力が村人たちに、悪魔の業として誤解されてしまったら? 彼女が、迫害の対象になってしまうかもしれない。
そして何よりも洋介自身の、男としてのプライドがそれを許さなかった。
祭りの夜、彼女に事実上拒絶された身だ。自分との間に壁を作り、会うことすら避けている彼女に今更どの面下げて助けを求めろと言うのか。しかも、助けてほしいのは恋敵であるはずのリリアなのだ。それはあまりにも身勝手で、虫のいい話ではないか。
プライドが彼に森へ行くことを躊躇させた。
しかし、リリアの容態は刻一刻と悪化していく。呼吸はますます浅くなり、意識も朦朧とし始めている。彼女の弱々しい呼吸を聞きながら、洋介の心の中で天秤が大きく揺れ動いていた。
自分のちっぽけなプライド。それとリリアのかけがえのない命。
比べるまでもない。
洋介は、歯を食いしばり、ついに決断した。プライドなど、どうでもいい。今、一番大切なのはリリアの命だ。彼女を失うことの方が、何千倍も、何万倍も、怖い。
洋介は、リリアの父親である村長に、後を託すと、家を飛び出した。夜の闇に紛れて、彼は、森へと走った。凍てつくような冬の風が、彼の頬を容赦なく打ちつける。
森の入り口に立ち、彼は一瞬ためらった。エリアーナに拒絶されたらどうしよう。罵られても仕方がない。それでも行くしかないのだ。
彼は、かつて、エリアーナと何度も歩いた道を、記憶だけを頼りに進んでいった。二人だけの聖域であった、あの泉のほとりへ。しかし、そこに彼女の姿はなかった。月光に照らされた泉が星屑を散りばめたように、静かに輝いているだけだった。
「エリアーナ!」
洋介は、必死に叫んだ。
「エリアーナ、どこだ! 頼む、出てきてくれ! 話があるんだ!」
彼の声は森の静寂に、虚しく吸い込まれていく。木霊すら返ってこない。彼女は、もう、この場所にさえ来ていないのだろうか。自分のことを完全に忘れようとしているのだろうか。絶望が彼の心を再び支配しようとした。
諦めかけて、その場に崩れ落ちそうになった、その時。
背後の巨大な夜樫の木の陰から、鈴を転がすような、しかし、氷のように冷たい声が聞こえた。
「⋯⋯私に何か用ですか。人間のあなたが、このような森の奥深くまで」
振り返ると、そこにエリアーナが立っていた。
月光を背に受け、その輪郭は青白く光っている。その表情は、以前よりもさらに硬く、冷たく、まるで美しい氷の彫像のようだった。彼女の瞳には、何の感情も浮かんでいなかった。
「エリアーナ⋯⋯! よかった、会えて⋯⋯」
洋介は、安堵と切実な思いで、彼女に駆け寄ろうとした。しかし、彼女の冷たい視線が彼をその場に縫い付けた。
「頼む、助けてくれ!」
洋介は、たまらずその場に膝をついた。土下座をするように、深く頭を下げた。
「村で、病が流行っているんだ。皆、苦しんでいる。リリアも⋯⋯リリアも、今、死にかけている! 君の力で、彼女を、村を、救ってほしい! この通りだ、お願いだ!」
エリアーナは、そんな彼の姿を、無表情のまま、ただ、見下ろしていた。リリア、という名を聞いた瞬間も、彼女の表情は、ピクリとも動かなかった。
長い、長い、沈黙が、二人を支配した。聞こえるのは、風が木々を揺らす音と、洋介の、荒い息遣いだけだった。
やがて、エリアーナの赤い唇がゆっくりと開かれた。
「⋯⋯なぜ、私が?」
その声は、冬の泉の水のように、冷え冷えとしていた。
「あなたは、私ではなく、あの子を選んだはず。人間の女と、人間としての幸せを。それに、私は、人間を助ける義理など、ありません。彼らが、どうなろうと、私の知ったことではないわ」
エリアーナの刃物のように冷たい言葉が、洋介の心を、容赦なく抉る。分かっていた。そう言われることは、覚悟していた。しかし、実際に、彼女の口から、その言葉を聞くと、全身の血が、逆流するような思いだった。
それでも、彼は、諦めなかった。
「分かっている! 俺が君を傷つけたことは、分かっている! 俺が君を拒絶し、君に甘え、君を苦しめた! 全部、分かっているつもりだ! でも、頼む! このままでは、皆死んでしまうんだ! リリアだけじゃない、罪のない、大勢の人々が苦しんでいるんだ! 君は、治癒の力を持っているんだろう!? 苦しむ者を見捨てることができるのか! それでも君は、森の癒し手なのか!?」
洋介の魂からの悲痛な叫びだった。その言葉に、エリアーナの氷の仮面がわずかに揺らいだ。彼女の瞳の奥で、何かが激しく葛藤しているのが見えた。
彼女はエルフだ。森の理と共に生きる癒し手だ。苦しむ者を見捨ててはおけない。それは彼女の、エルフとしての本能であり、使命だった。
しかし、彼女の心の中では、人間としての「小田春音」の、黒い感情が、激しく渦巻いていた。
なぜ、私が?
なぜ、私が、あなたの恋敵を、助けなければならないの?
あなたが、私を捨てて、選んだ女を。彼女が死ねば、あなたは、私の元へ、戻ってくるかもしれないのに。
そんな、醜い考えが、鎌首をもたげる。エルフとしての使命感と、人間としての嫉妬心。聖と俗。二つの感情が、エリアーナの中で、激しく、激しく、ぶつかり合っていた。彼女は、唇を、血が滲むほど、強く、噛み締めた。
長い、息が詰まるような沈黙の後。
エリアーナは、全ての感情を、心の奥底に押し殺し、静かに、口を開いた。
「⋯⋯いいでしょう。ただし、条件があります」
その声には、もう、何の温度も、感じられなかった。
「私が、あなたの村人を救ったら、あなたは、二度と私の前に現れないで。私のことを、私の存在を、あなたの記憶から、綺麗さっぱり、消し去ってください」
それは、エリアーナが自分の心を、自らの手で殺して絞り出した、あまりにも、あまりにも、悲しい条件だった。彼を救うための唯一の方法が、彼との永遠の決別だった。
第五章:癒しの光、決別の誓い
エリアーナが提示した条件は、死刑宣告にも等しい重さで、洋介の心にのしかかった。二度と会わない。
忘れてくれ。
その言葉の一つ一つが、凍てついた刃となって彼の魂を切り刻む。彼女の存在を、記憶から消し去る? そんなことが、できるはずがない。彼女こそが、彼の魂が、前世から、そしてこの世界に生まれ落ちてから、ずっと探し求めてきた、唯一無二の存在なのだ。彼女を忘れることは、自分自身の魂の半分を、自ら引き剥がすことに等しかった。
しかし、彼の背後には死の淵を彷徨うリリアの、そして多くの村人たちの、か細い命がかかっている。自分一人の感情、エリアーナへの愛のために、彼らを見殺しにすることなど断じてできなかった。それは人として、そして村のリーダーとしての、彼の存在意義そのものを根底から覆す行為だった。
「⋯⋯わかった」
洋介は、地面に落ちた枯れ葉を睨みつけながら、声を振り絞った。顔を上げれば、彼女の瞳を見てしまえば、この決意が鈍ってしまいそうだった。
「君が村を救ってくれるなら、俺は、君の前から永遠に姿を消す。君のことも⋯⋯忘れる努力を、しよう」
最後の言葉は、自分でも信じられないほど、か細く、惨めな響きを持っていた。「忘れる」と断言できず、「努力をする」としか言えない、自分の弱さ。その言葉を聞いたエリアーナの表情が、月光の下でわずかに歪んだように見えた。いや、それは彼の願望が見せた幻だったのかもしれない。彼女の顔は、依然として、美しい氷の仮面で覆われたままだった。
彼女は何も答えず、ただ静かに村の方角へと歩き始めた。洋介は、まるで罪人が刑場へ引かれていくような足取りで、その後ろに従った。
エリアーナが、村に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。
病の気配と死への恐怖で、澱のように沈んでいた村の空気が、彼女の登場によってピンと張り詰めた。偶然、彼女の姿を見つけた村人が息を飲み、その場に立ち尽くす。その驚きは瞬く間に、さざ波のように村全体へと広がっていった。家々の扉が軋みながら開き、人々が恐る恐る顔を覗かせる。
彼らが見たのは人間離れした、神々しいまでの美貌を持つ一人のエルフだった。月光を浴びた銀色の髪は、まるで光そのものを編み込んだかのようだった。森の木々と同じ緑色の瞳は、この世の全ての理を見通すかのように深く、そして静かだった。
エルフが、なぜこの村に?
村のリーダーである洋介様と共に?
誰もが畏怖と好奇、そして得体の知れないものへの恐怖が入り混じった、複雑な視線を彼女に注いでいた。囁き声があちこちから聞こえてくる。
エリアーナはそんな視線をまるで道端の石ころでも見るかのように、一切気にも留めなかった。彼女の意識はただ一点、村に渦巻く病の瘴気に集中していた。彼女は洋介を振り返ることもなくまっすぐに、村で最も死の匂いが濃い場所――診療所へと向かった。
診療所の中はこの世の地獄を凝縮したかのような惨状だった。狭い室内に所狭しと寝かされた人々。苦しげな咳、熱に浮かされたうわ言、そして、家族の無事を祈るすすり泣き。それらが混じり合い、重く、淀んだ空気を作り出していた。老医師は疲れ果てた表情で、ただなすすべもなく、その光景の前に立ち尽くしている。
エリアーナはその部屋の中心に静かに立った。そしてゆっくりと目を閉じた。全ての喧騒が彼女の世界から消え去っていく。彼女の意識は森の奥深く、自らの力の源泉へと、深く、深く潜っていった。
彼女がゆっくりと祈るように両手を広げると、その白い指先から柔らかな金色の光が蛍のように溢れ出した。最初は小さな光の粒子だったが、それは瞬く間に互いに結びつき、大きな光の奔流となって診療所全体を包み込んでいった。
その光は太陽のように熱くなく、月のように冷たくもない。それは生命そのものが持つ原初の温かさを持っていた。光が病に苦しむ人々の体を、優しく、優しく照らしていく。まるで母親が、熱に浮かされる我が子を慈しむように。すると、信じられない変化が起こり始めた。
激しく咳き込んでいた老人の胸が、穏やかに上下し始めた。高熱にうなされていた子供の額から、玉の汗が流れ落ち、その表情が和らいでいく。死人のように青白かった女の頬に、微かに血の気が戻っていく。
診療所の外で、固唾を飲んで見守っていた村人たちから驚きの声が上がる。それは、もはや魔法という言葉では説明しきれない、神の御業そのものだった。
エリアーナは目を開けることなく診療所を出ると、村の中をゆっくりと歩き始めた。一軒、また一軒と病人が眠る家を訪れ、その癒しの光で中を満たしていく。彼女が通り過ぎた後には、まるで春の嵐が全てを洗い流したかのように、清浄な空気が残された。
そして最後に、彼女はリリアが眠る村長の家へと向かった。
家の中では洋介と村長が、祈るような気持ちでリリアを見守っていた。リリアは、もはやほとんど呼吸をしていないかのように、か細い息を繰り返しているだけだった。その命の灯火は、今にも風に吹き消されてしまいそうだった。
エリアーナは部屋に入ると、リリアの枕元に静かに座った。そして、その熱い額にためらうことなく、そっと手を置いた。
彼女の手から放たれる、ひときわ強い金色の光が、リリアの体を繭のように、完全に包み込んだ。その光景を、洋介は息をすることさえ忘れて、ただ見守っていた。エリアーナの横顔は相変わらず無表情だったが、その瞳の奥には、深い、深い悲しみの色が揺らめいているように見えた。
(彼女は、どんな気持ちでリリアを癒しているのだろうか)
嫉妬、憎しみ、そういった感情を全て押し殺し、ただ、癒し手としての使命を全うしている。その気高い魂の在り方に洋介は胸を打たれ、同時に自分の無力さと罪深さを、改めて痛感させられた。
しばらくして奇跡が起こった。
リリアの青白かった唇に、ほんのりと赤みが差した。彼女の瞼が、かすかにぴくりと動いた。そしてゆっくりと、その瞳が開かれたのだ。
焦点の合わなかった瞳が、次第に光を取り戻し、そこに、心配そうに覗き込む洋介の顔を映し出した。
「⋯⋯ようすけ⋯⋯? わたし、どうして⋯⋯? 夢を、見ていたような⋯⋯」
「リリア!」
洋介は安堵のあまり、彼女の手を両手で強く握りしめた。涙が、後から後から溢れてくる。
「よかった⋯⋯! 本当に、よかった⋯⋯!」
リリアは、まだぼんやりとした頭で不思議そうに部屋の中に立つ、見慣れぬ女性を見つめていた。月光を背負い、まるで女神のように静かに佇んでいる。
「あの、かたは⋯⋯?」
「彼女が、君を、村を救ってくれたんだ。森のエルフ、エリアーナさんだ」
リリアは、洋介の言葉を聞くと、まだ衰弱しきっている体で、必死にベッドから起き上がろうとした。
「ありがとうございます、エリアーナ様。あなた様のおかげで、私の命は助かりました。このご恩は、一生忘れません」
リリアの純粋で、穢れのない感謝の言葉。
その言葉が、エリアーナの心に、小さな、しかし、鋭い棘のようにチクリと刺さった。自分は嫉妬心からこの娘を、心のどこかで見殺しにしたいとさえ願ってしまったのだ。それなのにこの娘は、こんなにも真っ直ぐな感謝を自分に向けてくれている。その純粋さが、エリアーナを深く苛んだ。
エリアーナは何も答えず、ただ静かに一礼すると部屋を出ていこうとした。使命は終わった。あとは約束通り、この村から、彼の人生から、永遠に姿を消すだけだ。
その時、洋介が彼女の前に立ちはだかった。
「エリアーナ、待ってくれ」
彼の声は、決意に満ちていた。
「約束は、守る。だが、最後に、一つだけ、聞かせてほしい」
洋介はエリアーナの、感情の読めない緑色の瞳を真っ直ぐに射抜くように見つめた。
「君は、俺のことを、本当に、忘れられるのか?」
その問いは彼に残された最後の、そして唯一の抵抗だった。忘れるな、と言いたい気持ちを必死で飲み込んで絞り出した問いだった。
その問いにエリアーナは、答えることができなかった。
忘れられるはずがない。
どうして忘れられるというのか。
この魂に、深く、深く、刻み込まれた愛の記憶を。百二十年もの間、ただ彼だけを想い続けてきたこの心を。
どうやって、消し去れというのか。
しかし、それを口にすることはできなかった。それを認めれば、この決意が揺らいでしまう。彼との間に断ち切れない甘い未練が残ってしまう。それは彼を苦しめるだけだ。
「⋯⋯それは、あなたには、関係のないことです」
そう答えるのが精一杯だった。彼女は自分の心を殺し続けた。
その冷たい言葉を聞いた洋介は、まるで全身の力が抜けていくようだった。彼は自嘲気味に、ふっと笑った。
「そうか⋯⋯。そうだな。もう、俺には関係のないこと、だ」
彼は、ゆっくりと道を開けた。
エリアーナは彼の横をすり抜けるようにして村を後にした。もう、二度と振り返らない。彼の顔を見てはいけない。これが最後の別れなのだから。
森へと帰る暗い夜道を一人、歩きながら。
エリアーナの美しい瞳から、こらえきれなかった涙が止めどなく、止めどなく溢れ出した。声にならない嗚咽が、彼女の喉を締め付けた。
これでよかったのだ。
彼は人間の女性と結ばれ、人間としての、短いけれど温かい幸せを生きるべきなのだ。自分のような、異形で悠久の時を生きる化け物が、彼の限られた貴重な人生を縛り付けてはならない。しかし心は正直だった。
洋介を失いたくない。彼のいない世界で、これから、何百年、何千年と、この孤独を抱えて生きていかなければならないのか。その、あまりにも長すぎる時間を思うと気が遠くなるようだった。
村では奇跡的な回復を遂げた人々が、エリアーナを「森の女神」と崇め、感謝の祈りを捧げていた。
リリアも順調に回復し、以前のような太陽のような明るい笑顔を取り戻していた。そして、村人たちの誰もが期待した通り、洋介とリリアは数週間後、正式に婚約を発表した。
その知らせは、森を渡る風の便りに乗ってエリアーナの耳にも届いた。彼女は、あの二人だけの聖域だった泉のほとりで、一人その知らせを聞いた。
胸にぽっかりと大きな修復不可能な穴が開いたような、空虚感。
しかし、不思議なことに涙はもう一滴も出なかった。流すべき涙は、あの夜、全て流し尽くしてしまったのかもしれない。
エリアーナは、静かな水面に映る自分の顔を見つめた。そこには、百二十年前と、何一つ変わらない、若く美しいエルフの顔があった。しかし、その瞳の奥には人間の一生分よりも、遥かに、遥かに、深い悲しみが、静かに、そして永遠に淀んでいた。
「さようなら、洋介」
エリアーナは、水面に映った、悲しい女に、そう、呟いた。
「私の、たった一人の愛した人」
彼女は自分の中に残っていた、「小田春音」の最後の欠片に、そっと別れを告げた。その瞬間から彼女はただの森の癒し手、エリアーナとして永遠の時を生きていくことを誓ったのだ。
忘れてくれ。
その言葉の一つ一つが、凍てついた刃となって彼の魂を切り刻む。彼女の存在を、記憶から消し去る? そんなことが、できるはずがない。彼女こそが、彼の魂が、前世から、そしてこの世界に生まれ落ちてから、ずっと探し求めてきた、唯一無二の存在なのだ。彼女を忘れることは、自分自身の魂の半分を、自ら引き剥がすことに等しかった。
しかし、彼の背後には死の淵を彷徨うリリアの、そして多くの村人たちの、か細い命がかかっている。自分一人の感情、エリアーナへの愛のために、彼らを見殺しにすることなど断じてできなかった。それは人として、そして村のリーダーとしての、彼の存在意義そのものを根底から覆す行為だった。
「⋯⋯わかった」
洋介は、地面に落ちた枯れ葉を睨みつけながら、声を振り絞った。顔を上げれば、彼女の瞳を見てしまえば、この決意が鈍ってしまいそうだった。
「君が村を救ってくれるなら、俺は、君の前から永遠に姿を消す。君のことも⋯⋯忘れる努力を、しよう」
最後の言葉は、自分でも信じられないほど、か細く、惨めな響きを持っていた。「忘れる」と断言できず、「努力をする」としか言えない、自分の弱さ。その言葉を聞いたエリアーナの表情が、月光の下でわずかに歪んだように見えた。いや、それは彼の願望が見せた幻だったのかもしれない。彼女の顔は、依然として、美しい氷の仮面で覆われたままだった。
彼女は何も答えず、ただ静かに村の方角へと歩き始めた。洋介は、まるで罪人が刑場へ引かれていくような足取りで、その後ろに従った。
エリアーナが、村に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。
病の気配と死への恐怖で、澱のように沈んでいた村の空気が、彼女の登場によってピンと張り詰めた。偶然、彼女の姿を見つけた村人が息を飲み、その場に立ち尽くす。その驚きは瞬く間に、さざ波のように村全体へと広がっていった。家々の扉が軋みながら開き、人々が恐る恐る顔を覗かせる。
彼らが見たのは人間離れした、神々しいまでの美貌を持つ一人のエルフだった。月光を浴びた銀色の髪は、まるで光そのものを編み込んだかのようだった。森の木々と同じ緑色の瞳は、この世の全ての理を見通すかのように深く、そして静かだった。
エルフが、なぜこの村に?
村のリーダーである洋介様と共に?
誰もが畏怖と好奇、そして得体の知れないものへの恐怖が入り混じった、複雑な視線を彼女に注いでいた。囁き声があちこちから聞こえてくる。
エリアーナはそんな視線をまるで道端の石ころでも見るかのように、一切気にも留めなかった。彼女の意識はただ一点、村に渦巻く病の瘴気に集中していた。彼女は洋介を振り返ることもなくまっすぐに、村で最も死の匂いが濃い場所――診療所へと向かった。
診療所の中はこの世の地獄を凝縮したかのような惨状だった。狭い室内に所狭しと寝かされた人々。苦しげな咳、熱に浮かされたうわ言、そして、家族の無事を祈るすすり泣き。それらが混じり合い、重く、淀んだ空気を作り出していた。老医師は疲れ果てた表情で、ただなすすべもなく、その光景の前に立ち尽くしている。
エリアーナはその部屋の中心に静かに立った。そしてゆっくりと目を閉じた。全ての喧騒が彼女の世界から消え去っていく。彼女の意識は森の奥深く、自らの力の源泉へと、深く、深く潜っていった。
彼女がゆっくりと祈るように両手を広げると、その白い指先から柔らかな金色の光が蛍のように溢れ出した。最初は小さな光の粒子だったが、それは瞬く間に互いに結びつき、大きな光の奔流となって診療所全体を包み込んでいった。
その光は太陽のように熱くなく、月のように冷たくもない。それは生命そのものが持つ原初の温かさを持っていた。光が病に苦しむ人々の体を、優しく、優しく照らしていく。まるで母親が、熱に浮かされる我が子を慈しむように。すると、信じられない変化が起こり始めた。
激しく咳き込んでいた老人の胸が、穏やかに上下し始めた。高熱にうなされていた子供の額から、玉の汗が流れ落ち、その表情が和らいでいく。死人のように青白かった女の頬に、微かに血の気が戻っていく。
診療所の外で、固唾を飲んで見守っていた村人たちから驚きの声が上がる。それは、もはや魔法という言葉では説明しきれない、神の御業そのものだった。
エリアーナは目を開けることなく診療所を出ると、村の中をゆっくりと歩き始めた。一軒、また一軒と病人が眠る家を訪れ、その癒しの光で中を満たしていく。彼女が通り過ぎた後には、まるで春の嵐が全てを洗い流したかのように、清浄な空気が残された。
そして最後に、彼女はリリアが眠る村長の家へと向かった。
家の中では洋介と村長が、祈るような気持ちでリリアを見守っていた。リリアは、もはやほとんど呼吸をしていないかのように、か細い息を繰り返しているだけだった。その命の灯火は、今にも風に吹き消されてしまいそうだった。
エリアーナは部屋に入ると、リリアの枕元に静かに座った。そして、その熱い額にためらうことなく、そっと手を置いた。
彼女の手から放たれる、ひときわ強い金色の光が、リリアの体を繭のように、完全に包み込んだ。その光景を、洋介は息をすることさえ忘れて、ただ見守っていた。エリアーナの横顔は相変わらず無表情だったが、その瞳の奥には、深い、深い悲しみの色が揺らめいているように見えた。
(彼女は、どんな気持ちでリリアを癒しているのだろうか)
嫉妬、憎しみ、そういった感情を全て押し殺し、ただ、癒し手としての使命を全うしている。その気高い魂の在り方に洋介は胸を打たれ、同時に自分の無力さと罪深さを、改めて痛感させられた。
しばらくして奇跡が起こった。
リリアの青白かった唇に、ほんのりと赤みが差した。彼女の瞼が、かすかにぴくりと動いた。そしてゆっくりと、その瞳が開かれたのだ。
焦点の合わなかった瞳が、次第に光を取り戻し、そこに、心配そうに覗き込む洋介の顔を映し出した。
「⋯⋯ようすけ⋯⋯? わたし、どうして⋯⋯? 夢を、見ていたような⋯⋯」
「リリア!」
洋介は安堵のあまり、彼女の手を両手で強く握りしめた。涙が、後から後から溢れてくる。
「よかった⋯⋯! 本当に、よかった⋯⋯!」
リリアは、まだぼんやりとした頭で不思議そうに部屋の中に立つ、見慣れぬ女性を見つめていた。月光を背負い、まるで女神のように静かに佇んでいる。
「あの、かたは⋯⋯?」
「彼女が、君を、村を救ってくれたんだ。森のエルフ、エリアーナさんだ」
リリアは、洋介の言葉を聞くと、まだ衰弱しきっている体で、必死にベッドから起き上がろうとした。
「ありがとうございます、エリアーナ様。あなた様のおかげで、私の命は助かりました。このご恩は、一生忘れません」
リリアの純粋で、穢れのない感謝の言葉。
その言葉が、エリアーナの心に、小さな、しかし、鋭い棘のようにチクリと刺さった。自分は嫉妬心からこの娘を、心のどこかで見殺しにしたいとさえ願ってしまったのだ。それなのにこの娘は、こんなにも真っ直ぐな感謝を自分に向けてくれている。その純粋さが、エリアーナを深く苛んだ。
エリアーナは何も答えず、ただ静かに一礼すると部屋を出ていこうとした。使命は終わった。あとは約束通り、この村から、彼の人生から、永遠に姿を消すだけだ。
その時、洋介が彼女の前に立ちはだかった。
「エリアーナ、待ってくれ」
彼の声は、決意に満ちていた。
「約束は、守る。だが、最後に、一つだけ、聞かせてほしい」
洋介はエリアーナの、感情の読めない緑色の瞳を真っ直ぐに射抜くように見つめた。
「君は、俺のことを、本当に、忘れられるのか?」
その問いは彼に残された最後の、そして唯一の抵抗だった。忘れるな、と言いたい気持ちを必死で飲み込んで絞り出した問いだった。
その問いにエリアーナは、答えることができなかった。
忘れられるはずがない。
どうして忘れられるというのか。
この魂に、深く、深く、刻み込まれた愛の記憶を。百二十年もの間、ただ彼だけを想い続けてきたこの心を。
どうやって、消し去れというのか。
しかし、それを口にすることはできなかった。それを認めれば、この決意が揺らいでしまう。彼との間に断ち切れない甘い未練が残ってしまう。それは彼を苦しめるだけだ。
「⋯⋯それは、あなたには、関係のないことです」
そう答えるのが精一杯だった。彼女は自分の心を殺し続けた。
その冷たい言葉を聞いた洋介は、まるで全身の力が抜けていくようだった。彼は自嘲気味に、ふっと笑った。
「そうか⋯⋯。そうだな。もう、俺には関係のないこと、だ」
彼は、ゆっくりと道を開けた。
エリアーナは彼の横をすり抜けるようにして村を後にした。もう、二度と振り返らない。彼の顔を見てはいけない。これが最後の別れなのだから。
森へと帰る暗い夜道を一人、歩きながら。
エリアーナの美しい瞳から、こらえきれなかった涙が止めどなく、止めどなく溢れ出した。声にならない嗚咽が、彼女の喉を締め付けた。
これでよかったのだ。
彼は人間の女性と結ばれ、人間としての、短いけれど温かい幸せを生きるべきなのだ。自分のような、異形で悠久の時を生きる化け物が、彼の限られた貴重な人生を縛り付けてはならない。しかし心は正直だった。
洋介を失いたくない。彼のいない世界で、これから、何百年、何千年と、この孤独を抱えて生きていかなければならないのか。その、あまりにも長すぎる時間を思うと気が遠くなるようだった。
村では奇跡的な回復を遂げた人々が、エリアーナを「森の女神」と崇め、感謝の祈りを捧げていた。
リリアも順調に回復し、以前のような太陽のような明るい笑顔を取り戻していた。そして、村人たちの誰もが期待した通り、洋介とリリアは数週間後、正式に婚約を発表した。
その知らせは、森を渡る風の便りに乗ってエリアーナの耳にも届いた。彼女は、あの二人だけの聖域だった泉のほとりで、一人その知らせを聞いた。
胸にぽっかりと大きな修復不可能な穴が開いたような、空虚感。
しかし、不思議なことに涙はもう一滴も出なかった。流すべき涙は、あの夜、全て流し尽くしてしまったのかもしれない。
エリアーナは、静かな水面に映る自分の顔を見つめた。そこには、百二十年前と、何一つ変わらない、若く美しいエルフの顔があった。しかし、その瞳の奥には人間の一生分よりも、遥かに、遥かに、深い悲しみが、静かに、そして永遠に淀んでいた。
「さようなら、洋介」
エリアーナは、水面に映った、悲しい女に、そう、呟いた。
「私の、たった一人の愛した人」
彼女は自分の中に残っていた、「小田春音」の最後の欠片に、そっと別れを告げた。その瞬間から彼女はただの森の癒し手、エリアーナとして永遠の時を生きていくことを誓ったのだ。
第六章:女神の涙、森の異変
洋介とリリアの婚約の知らせから数年の歳月が流れた。エリアーナはあの日以来、一度も森から出ることはなかった。洋介との決別の誓いを、彼女は固く守り続けていた。しかし、その心は癒えることのない傷口のように絶えず痛み続けていた。彼女は以前にも増して、治癒の魔法に没頭するようになった。傷ついた動物がいれば昼夜を問わず駆けつけ、その命を救った。まるで、他者を癒すことでしか、自分の心の痛みを紛らわすことができないかのように。
エルフの仲間たちは、そんな彼女の姿を憂慮の目で見守っていた。長老エルドランは何度も彼女に語りかけた。
「エリアーナよ、お前の悲しみは分かる。しかし、その悲しみにお前自身が飲み込まれてはならぬ。お前は、この森の希望なのだから」
しかし、エルドランの言葉もエリアーナの心には届かなかった。彼女の心は、厚い氷の壁に閉ざされてしまったかのようだった。
そんなある日、森に奇妙な異変が起こり始めた。生命力に満ち溢れていた木々が少しずつ枯れ始め、色鮮やかだった花々はその色彩を失っていった。森を流れる小川は、淀み、精霊たちの歌声も聞こえなくなった。森全体が深い悲しみに包まれているかのようだった。
エルフたちは、この異変の原因を探ろうとしたが、誰にも、その理由は分からなかった。ただ一つだけ確かなことがあった。異変はエリアーナが住む森の、最も深い場所から始まっているということだ。
エルドランは、エリアーナの元を訪れた。治癒の魔法に没頭する彼女の周りだけが、以前と変わらぬ生命力に満ちている。しかし、その一歩外側は、確実に、死の世界へと変わりつつあった。
「エリアーナよ、気づいておるか。お前の悲しみが森を枯らしているのだ」
エルドランの厳しい言葉に、エリアーナは、ハッとして顔を上げた。
「私の⋯悲しみが⋯?」
「そうだ。エルフは、自然と共にある存在。お前の心の状態が、そのまま、森に反映される。お前が、心を閉ざし、悲しみに沈めば、森もまた、生命力を失っていくのだ。お前が流す涙は、もはや、癒しの光ではない。森を蝕む、毒なのだ」
エルドランの言葉は、エリアーナの心に深く突き刺さった。自分のせいで、この美しい森が枯れようとしている。自分が仲間たちを苦しめている。その事実は彼女にとってあまりにも衝撃的だった。
「私は⋯⋯どうすれば⋯⋯」
「お前の心を解き放つのだ。悲しみも苦しみも、全て受け入れ、そして乗り越えよ。それが、お前に与えられた試練なのだ」
エルドランは、そう言うと静かにその場を立ち去った。一人残されたエリアーナは、呆然と枯れ始めた木々を見つめていた。
一方、人間の村では、洋介とリリアの間に、待望の男の子が生まれていた。村中が、祝福のムードに包まれていた。洋介は父親になり、建築士としても、村の発展に大きく貢献し、村人たちから、絶大な信頼を寄せられていた。彼は、誰もが羨むような、幸せな家庭を築いていた。
しかし、彼の心の奥底には常にエリアーナの影があった。リリアを愛している。息子も、もちろん可愛い。しかし、エリアーナへの想いは時間の経過と共に、薄れるどころか、むしろ鮮明になっていくようだった。
夜、一人で図面を引いていると、ふと窓の外に、彼女が立っているような気がして、何度も振り返ってしまう。森の方から風が吹いてくると、その風が彼女のメッセージを運んでくるような気がして耳を澄ましてしまう。
忘れると、誓ったはずなのに。彼女を忘れることなどできはしない。
そんなある夜、洋介は奇妙な夢を見た。エリアーナが住む森が枯れていく夢だ。美しい緑は失われ、大地はひび割れ、彼女は、その中心で一人泣いている。その涙が、黒い雫となって、大地に吸い込まれていく。そして、その雫が落ちた場所から森が腐敗していくのだ。
洋介は悪夢にうなされ飛び起きた。胸騒ぎがしてじっとしていられない。彼はリリアと息子が眠る寝室をそっと抜け出し、夜の闇の中、森へと向かった。エリアーナとの約束を破ることにためらいはなかった。彼女が危険な状態にある。その直感が彼を突き動かしていた。
森の入り口に立った洋介は息を飲んだ。夢で見た光景が、そのまま目の前に広がっていた。かつて生命力に満ち溢れていた森は見る影もなく、枯れ果て、不気味な静寂に包まれていた。
洋介はためらうことなく、森の奥深くへと足を踏み入れた。エリアーナの元へ。彼女を救わなければ。その一心で、彼は暗い森の中を走り続けた。
エルフの仲間たちは、そんな彼女の姿を憂慮の目で見守っていた。長老エルドランは何度も彼女に語りかけた。
「エリアーナよ、お前の悲しみは分かる。しかし、その悲しみにお前自身が飲み込まれてはならぬ。お前は、この森の希望なのだから」
しかし、エルドランの言葉もエリアーナの心には届かなかった。彼女の心は、厚い氷の壁に閉ざされてしまったかのようだった。
そんなある日、森に奇妙な異変が起こり始めた。生命力に満ち溢れていた木々が少しずつ枯れ始め、色鮮やかだった花々はその色彩を失っていった。森を流れる小川は、淀み、精霊たちの歌声も聞こえなくなった。森全体が深い悲しみに包まれているかのようだった。
エルフたちは、この異変の原因を探ろうとしたが、誰にも、その理由は分からなかった。ただ一つだけ確かなことがあった。異変はエリアーナが住む森の、最も深い場所から始まっているということだ。
エルドランは、エリアーナの元を訪れた。治癒の魔法に没頭する彼女の周りだけが、以前と変わらぬ生命力に満ちている。しかし、その一歩外側は、確実に、死の世界へと変わりつつあった。
「エリアーナよ、気づいておるか。お前の悲しみが森を枯らしているのだ」
エルドランの厳しい言葉に、エリアーナは、ハッとして顔を上げた。
「私の⋯悲しみが⋯?」
「そうだ。エルフは、自然と共にある存在。お前の心の状態が、そのまま、森に反映される。お前が、心を閉ざし、悲しみに沈めば、森もまた、生命力を失っていくのだ。お前が流す涙は、もはや、癒しの光ではない。森を蝕む、毒なのだ」
エルドランの言葉は、エリアーナの心に深く突き刺さった。自分のせいで、この美しい森が枯れようとしている。自分が仲間たちを苦しめている。その事実は彼女にとってあまりにも衝撃的だった。
「私は⋯⋯どうすれば⋯⋯」
「お前の心を解き放つのだ。悲しみも苦しみも、全て受け入れ、そして乗り越えよ。それが、お前に与えられた試練なのだ」
エルドランは、そう言うと静かにその場を立ち去った。一人残されたエリアーナは、呆然と枯れ始めた木々を見つめていた。
一方、人間の村では、洋介とリリアの間に、待望の男の子が生まれていた。村中が、祝福のムードに包まれていた。洋介は父親になり、建築士としても、村の発展に大きく貢献し、村人たちから、絶大な信頼を寄せられていた。彼は、誰もが羨むような、幸せな家庭を築いていた。
しかし、彼の心の奥底には常にエリアーナの影があった。リリアを愛している。息子も、もちろん可愛い。しかし、エリアーナへの想いは時間の経過と共に、薄れるどころか、むしろ鮮明になっていくようだった。
夜、一人で図面を引いていると、ふと窓の外に、彼女が立っているような気がして、何度も振り返ってしまう。森の方から風が吹いてくると、その風が彼女のメッセージを運んでくるような気がして耳を澄ましてしまう。
忘れると、誓ったはずなのに。彼女を忘れることなどできはしない。
そんなある夜、洋介は奇妙な夢を見た。エリアーナが住む森が枯れていく夢だ。美しい緑は失われ、大地はひび割れ、彼女は、その中心で一人泣いている。その涙が、黒い雫となって、大地に吸い込まれていく。そして、その雫が落ちた場所から森が腐敗していくのだ。
洋介は悪夢にうなされ飛び起きた。胸騒ぎがしてじっとしていられない。彼はリリアと息子が眠る寝室をそっと抜け出し、夜の闇の中、森へと向かった。エリアーナとの約束を破ることにためらいはなかった。彼女が危険な状態にある。その直感が彼を突き動かしていた。
森の入り口に立った洋介は息を飲んだ。夢で見た光景が、そのまま目の前に広がっていた。かつて生命力に満ち溢れていた森は見る影もなく、枯れ果て、不気味な静寂に包まれていた。
洋介はためらうことなく、森の奥深くへと足を踏み入れた。エリアーナの元へ。彼女を救わなければ。その一心で、彼は暗い森の中を走り続けた。
第七章:二つの世界の選択
枯れ果てた森の奥深く、エリアーナは、泉のほとりに、ただ一人、座り込んでいた。彼女の周りだけが、かろうじて、緑の名残を留めている。しかし、その緑も、今や、消えかかろうとしていた。自分の悲しみが、この美しい森を、死に追いやっている。その罪悪感に、エリアーナは、打ちのめされていた。もう、私には、生きている資格はない。私が、消えれば、森は、元の姿を取り戻すだろうか。エリアーナは、泉の水面に映る、自分のやつれた顔を見つめながら、静かに、自らの命を絶つことを考えていた。
その時、背後で枯れ葉を踏む音がした。振り返るとそこに洋介が立っていた。数年ぶりに見る彼は、以前よりも精悍な顔つきになり、口元には髭をたくわえていた。彼の顔には人間としての、確かな年月が刻まれていた。
「洋介⋯⋯! どうして、ここに⋯⋯? 約束を、破るのですか?」
エリアーナの声は、か細く震えていた。
「約束よりも、君の方が大事だ。君が、危険な状態にあると、感じたんだ」
洋介は、エリアーナのそばに駆け寄り、その痩せた肩を、強く抱きしめた。
「なんて、酷い顔をしているんだ⋯⋯。一体、何があったんだ?」
「私のせいなの⋯⋯私の悲しみが、森を、こんな姿に変えてしまったの⋯⋯」
エリアーナは、洋介の胸の中で、子供のように泣きじゃくった。洋介は、何も言わず、ただ、彼女の背中を、優しくさすり続けていた。
「もう、いいんだ、春音。もう、一人で、苦しまなくていい」
洋介の温かい言葉に、エリアーナの心に張っていた氷の壁が、少しずつ、溶けていくようだった。
「洋介⋯⋯私、どうしたらいいか分からないの。あなたを、忘れることもできない。でも、あなたと一緒にいることもできない。私の存在が、あなたを、そして、この森を、苦しめている⋯⋯」
「俺も、同じだよ、春音。俺も、君を、一日たりとも、忘れたことはなかった。リリアや息子を愛している気持ちに、嘘はない。だが、君への想いは、それとは、 全く別のものなんだ。俺の魂が、君を、求めているんだ」
洋介は、エリアーナの顔を両手で包み込み、その瞳を真っ直ぐに見つめた。
「もう、自分たちの気持ちに嘘をつくのは、やめにしよう。俺は君を愛している。春音、いや、エリアーナ。君だけを、愛している」
洋介の告白に、エリアーナの目から、再び、涙が溢れ出した。しかし、それは、悲しみの涙ではなかった。喜びと、安堵の涙だった。
その時、二人の周りで、奇跡が起こった。エリアーナの涙が、地面に落ちた瞬間、その場所から、柔らかな光が放たれ、枯れていた草花が、一斉に、息を吹き返したのだ。エリアーナの心が、解き放たれたことで、森が、生命力を取り戻し始めたのだ。
「森が⋯⋯元に戻っていく⋯⋯」
エリアーナは、信じられないという表情で、周りを見渡した。枯れ木には、新しい芽が吹き、小川には、清らかな水が流れ始めていた。
「君の心が、森を、癒しているんだ」
洋介は、微笑みながら、エリアーナの手を、強く握った。
しかし、二人の問題が、解決したわけではない。洋介には、人間の世界に、愛する家族がいる。エリアーナは、この森を、守っていかなければならない。そして、何よりも、二人の間には、あまりにも長い、時間の隔たりがある。
「洋介、あなたには、帰る場所があるわ。リリアさんと、お子さんが、待っている」
「分かっている。だが、もう、君と離れたくないんだ」
「でも⋯⋯」
二人が、答えを見つけられずにいると、そこに、長老エルドランが静かに姿を現した。
「二人の選択肢は二つある」
エルドランは、厳かな口調で、語り始めた。
「一つは、人間である洋介が、全てを捨て、この森で、エリアーナと共に生きること。しかし、お前は、人間の短い寿命を、この森で、静かに終えることになる。家族にも、二度と会うことはできぬ」
エルドランは次に、エリアーナの方を向いた。
「もう一つは、エルフであるエリアーナが、エルフであることをやめ、人間として、洋介と共に、人間の世界で生きることだ。しかし、そのためには、お前は、悠久の時を生きる力と、治癒の魔法を、全て、手放さなければならない。そして、人間として、老い、病み、死ぬという、運命を受け入れることになる」
エルドランの言葉に、二人は息を飲んだ。あまりにも究極の選択だった。
「どちらの道を選ぶにせよ、それは、お前たちの、魂の決断だ。よく、考えるがよい」
エルドランはそう言うと、再び森の奥へと姿を消した。
残された二人は、ただ黙ってお互いの顔を見つめ合うだけだった。どちらの道を選んでも、あまりにも大きな代償を払わなければならない。二人の愛は今、あまりにも過酷な試練に立たされていた。
その時、背後で枯れ葉を踏む音がした。振り返るとそこに洋介が立っていた。数年ぶりに見る彼は、以前よりも精悍な顔つきになり、口元には髭をたくわえていた。彼の顔には人間としての、確かな年月が刻まれていた。
「洋介⋯⋯! どうして、ここに⋯⋯? 約束を、破るのですか?」
エリアーナの声は、か細く震えていた。
「約束よりも、君の方が大事だ。君が、危険な状態にあると、感じたんだ」
洋介は、エリアーナのそばに駆け寄り、その痩せた肩を、強く抱きしめた。
「なんて、酷い顔をしているんだ⋯⋯。一体、何があったんだ?」
「私のせいなの⋯⋯私の悲しみが、森を、こんな姿に変えてしまったの⋯⋯」
エリアーナは、洋介の胸の中で、子供のように泣きじゃくった。洋介は、何も言わず、ただ、彼女の背中を、優しくさすり続けていた。
「もう、いいんだ、春音。もう、一人で、苦しまなくていい」
洋介の温かい言葉に、エリアーナの心に張っていた氷の壁が、少しずつ、溶けていくようだった。
「洋介⋯⋯私、どうしたらいいか分からないの。あなたを、忘れることもできない。でも、あなたと一緒にいることもできない。私の存在が、あなたを、そして、この森を、苦しめている⋯⋯」
「俺も、同じだよ、春音。俺も、君を、一日たりとも、忘れたことはなかった。リリアや息子を愛している気持ちに、嘘はない。だが、君への想いは、それとは、 全く別のものなんだ。俺の魂が、君を、求めているんだ」
洋介は、エリアーナの顔を両手で包み込み、その瞳を真っ直ぐに見つめた。
「もう、自分たちの気持ちに嘘をつくのは、やめにしよう。俺は君を愛している。春音、いや、エリアーナ。君だけを、愛している」
洋介の告白に、エリアーナの目から、再び、涙が溢れ出した。しかし、それは、悲しみの涙ではなかった。喜びと、安堵の涙だった。
その時、二人の周りで、奇跡が起こった。エリアーナの涙が、地面に落ちた瞬間、その場所から、柔らかな光が放たれ、枯れていた草花が、一斉に、息を吹き返したのだ。エリアーナの心が、解き放たれたことで、森が、生命力を取り戻し始めたのだ。
「森が⋯⋯元に戻っていく⋯⋯」
エリアーナは、信じられないという表情で、周りを見渡した。枯れ木には、新しい芽が吹き、小川には、清らかな水が流れ始めていた。
「君の心が、森を、癒しているんだ」
洋介は、微笑みながら、エリアーナの手を、強く握った。
しかし、二人の問題が、解決したわけではない。洋介には、人間の世界に、愛する家族がいる。エリアーナは、この森を、守っていかなければならない。そして、何よりも、二人の間には、あまりにも長い、時間の隔たりがある。
「洋介、あなたには、帰る場所があるわ。リリアさんと、お子さんが、待っている」
「分かっている。だが、もう、君と離れたくないんだ」
「でも⋯⋯」
二人が、答えを見つけられずにいると、そこに、長老エルドランが静かに姿を現した。
「二人の選択肢は二つある」
エルドランは、厳かな口調で、語り始めた。
「一つは、人間である洋介が、全てを捨て、この森で、エリアーナと共に生きること。しかし、お前は、人間の短い寿命を、この森で、静かに終えることになる。家族にも、二度と会うことはできぬ」
エルドランは次に、エリアーナの方を向いた。
「もう一つは、エルフであるエリアーナが、エルフであることをやめ、人間として、洋介と共に、人間の世界で生きることだ。しかし、そのためには、お前は、悠久の時を生きる力と、治癒の魔法を、全て、手放さなければならない。そして、人間として、老い、病み、死ぬという、運命を受け入れることになる」
エルドランの言葉に、二人は息を飲んだ。あまりにも究極の選択だった。
「どちらの道を選ぶにせよ、それは、お前たちの、魂の決断だ。よく、考えるがよい」
エルドランはそう言うと、再び森の奥へと姿を消した。
残された二人は、ただ黙ってお互いの顔を見つめ合うだけだった。どちらの道を選んでも、あまりにも大きな代償を払わなければならない。二人の愛は今、あまりにも過酷な試練に立たされていた。
第八章:魂の決断、新たな誓い
エルドランが示した、二つの過酷な選択。洋介とエリアーナは、夜が明けるまで、語り合った。どちらの道を選ぶべきか、答えは、簡単には出なかった。洋介が人間としての生を捨て森で暮らす。それは、エリアーナと共にいられるという甘美な響きを持っていた。しかし、それは同時に、彼が築き上げてきた全てを、捨てることを意味していた。愛する妻、リリア。生まれたばかりの息子。そして、彼を信頼し、慕ってくれる、村の人々。彼らを、裏切ることなど、できるはずがなかった。
「俺にはできない。リリアと息子を見捨てることなんてできない。彼らにも俺に対する愛情と信頼がある。それを踏みにじることは俺の良心が許さない」
洋介は苦渋の表情でそう言った。エリアーナも黙って頷いた。彼女も彼に、そんな非情な選択をしてほしくなかった。
では、エリアーナがエルフであることをやめ、人間になるのか。悠久の時を生きる力と奇跡の魔法を全て手放し、人間として老い、死ぬ運命を受け入れる。それは彼女が、エリアーナとして生きてきた百数十年という歳月を、全て否定することに等しかった。しかし、エリアーナの心は決まっていた。
「私、人間になるわ」
彼女の言葉に、洋介は驚いて顔を上げた。
「エリアーナ、本気か!? 君は、エルフとしての、全てを失うんだぞ! それは、君にとって、死ぬことよりも、辛いことかもしれないんだぞ!」
「いいえ、辛くないわ。私は、あなたと一緒に、同じ時間を、生きたいの。あなたと同じように、歳をとり、同じように、シワを刻み、そして、いつか、あなたの腕の中で、静かに、眠りたい。それが、私の、たった一つの、望みなの」
エリアーナの瞳は、固い決意に満ちていた。彼女は、百数年という孤独な時間の中で、ずっと、それを、望んできたのだ。洋介と、同じ時を、生きることを。
「でも、そしたら、君は⋯⋯」
「分かっているわ。私は、あなたよりも、早く、死ぬかもしれない。病気になるかもしれない。でも、それでもいいの。あなたと一緒にいられる、限られた時間の方が、あなたと離れて過ごす、永遠の時間よりも、ずっと、価値があるわ」
エリアーナの言葉に、洋介は、涙を止めることができなかった。自分のために、彼女が、どれほど大きな犠牲を、払おうとしているのか。その愛の深さに、胸が、締め付けられた。
「本当に、いいのか? 俺は、君を、幸せにできるだろうか⋯⋯」
「あなたが、そばにいてくれる。それだけで、私は、世界一、幸せよ」
二人は、強く、抱きしめ合った。そして、新たな誓いを、立てた。エリアーナは、エルドランの元を訪れ、自分の決意を告げた。エルドランは、何も言わず、ただ、悲しそうな目で、彼女を見つめていた。
「⋯⋯それが、お前の魂の決断なのだな」
「はい。私は、彼と、人間として生きていきます」
「よかろう。ならば、この泉の水を飲むがよい。この水を飲めば、お前はエルフの力を全て失い、ただの人間の女になるだろう。二度とエルフには戻れぬぞ」
エルドランが指差した泉は、森の最も神聖な場所にあり、月光を浴びて、神秘的な輝きを放っていた。
エリアーナは、ためらうことなく泉の水を両手ですくい口に含んだ。その瞬間、彼女の体から金色の光がふわりと抜け出ていくのが見えた。長く尖っていた耳は丸みを帯び、陽の光に透けるようだった白い肌も健康的な人間の肌の色へと変わっていった。
彼女はもう、エルフのエリアーナではなかった。ただの人間の女、春音だった。
力を失った春音は、急に疲労感を覚え、その場に崩れ落ちそうになった。洋介が慌てて彼女の体を支えた。
「春音! 大丈夫か!?」
「ええ、大丈夫⋯⋯。ただ、少し眠いだけ⋯⋯」
春音は洋介の腕の中で、安らかな表情で眠りについた。洋介は眠る春音を抱きかかえ、エルドランに深く頭を下げた。
「ありがとうございました。彼女のことは俺が命に代えても守ります」
「うむ。行け。そして二度とこの森に足を踏み入れるな」
エルドランはそう言うと背を向けた。その背中はどこか寂しげだった。
洋介は、春音を抱きかかえたまま人間の村へと帰っていった。彼の心の中には、春音と共に生きられる喜びと、そして、これからリリアに全てを話さなければならないという重い責任が混じり合っていた。
穏やかではない未来が待っていることは分かっていた。しかし、それでも、彼は、春音の手を決して離さないと、心に誓っていた。
「俺にはできない。リリアと息子を見捨てることなんてできない。彼らにも俺に対する愛情と信頼がある。それを踏みにじることは俺の良心が許さない」
洋介は苦渋の表情でそう言った。エリアーナも黙って頷いた。彼女も彼に、そんな非情な選択をしてほしくなかった。
では、エリアーナがエルフであることをやめ、人間になるのか。悠久の時を生きる力と奇跡の魔法を全て手放し、人間として老い、死ぬ運命を受け入れる。それは彼女が、エリアーナとして生きてきた百数十年という歳月を、全て否定することに等しかった。しかし、エリアーナの心は決まっていた。
「私、人間になるわ」
彼女の言葉に、洋介は驚いて顔を上げた。
「エリアーナ、本気か!? 君は、エルフとしての、全てを失うんだぞ! それは、君にとって、死ぬことよりも、辛いことかもしれないんだぞ!」
「いいえ、辛くないわ。私は、あなたと一緒に、同じ時間を、生きたいの。あなたと同じように、歳をとり、同じように、シワを刻み、そして、いつか、あなたの腕の中で、静かに、眠りたい。それが、私の、たった一つの、望みなの」
エリアーナの瞳は、固い決意に満ちていた。彼女は、百数年という孤独な時間の中で、ずっと、それを、望んできたのだ。洋介と、同じ時を、生きることを。
「でも、そしたら、君は⋯⋯」
「分かっているわ。私は、あなたよりも、早く、死ぬかもしれない。病気になるかもしれない。でも、それでもいいの。あなたと一緒にいられる、限られた時間の方が、あなたと離れて過ごす、永遠の時間よりも、ずっと、価値があるわ」
エリアーナの言葉に、洋介は、涙を止めることができなかった。自分のために、彼女が、どれほど大きな犠牲を、払おうとしているのか。その愛の深さに、胸が、締め付けられた。
「本当に、いいのか? 俺は、君を、幸せにできるだろうか⋯⋯」
「あなたが、そばにいてくれる。それだけで、私は、世界一、幸せよ」
二人は、強く、抱きしめ合った。そして、新たな誓いを、立てた。エリアーナは、エルドランの元を訪れ、自分の決意を告げた。エルドランは、何も言わず、ただ、悲しそうな目で、彼女を見つめていた。
「⋯⋯それが、お前の魂の決断なのだな」
「はい。私は、彼と、人間として生きていきます」
「よかろう。ならば、この泉の水を飲むがよい。この水を飲めば、お前はエルフの力を全て失い、ただの人間の女になるだろう。二度とエルフには戻れぬぞ」
エルドランが指差した泉は、森の最も神聖な場所にあり、月光を浴びて、神秘的な輝きを放っていた。
エリアーナは、ためらうことなく泉の水を両手ですくい口に含んだ。その瞬間、彼女の体から金色の光がふわりと抜け出ていくのが見えた。長く尖っていた耳は丸みを帯び、陽の光に透けるようだった白い肌も健康的な人間の肌の色へと変わっていった。
彼女はもう、エルフのエリアーナではなかった。ただの人間の女、春音だった。
力を失った春音は、急に疲労感を覚え、その場に崩れ落ちそうになった。洋介が慌てて彼女の体を支えた。
「春音! 大丈夫か!?」
「ええ、大丈夫⋯⋯。ただ、少し眠いだけ⋯⋯」
春音は洋介の腕の中で、安らかな表情で眠りについた。洋介は眠る春音を抱きかかえ、エルドランに深く頭を下げた。
「ありがとうございました。彼女のことは俺が命に代えても守ります」
「うむ。行け。そして二度とこの森に足を踏み入れるな」
エルドランはそう言うと背を向けた。その背中はどこか寂しげだった。
洋介は、春音を抱きかかえたまま人間の村へと帰っていった。彼の心の中には、春音と共に生きられる喜びと、そして、これからリリアに全てを話さなければならないという重い責任が混じり合っていた。
穏やかではない未来が待っていることは分かっていた。しかし、それでも、彼は、春音の手を決して離さないと、心に誓っていた。
第九章:償いの日々、育まれる愛
洋介が眠る春音を抱いて村に帰った時、村は、夜明け前の静寂に包まれていた。彼は、まず、自分の家には向かわず、村はずれにある空き家へと向かった。春音をそっとベッドに寝かせると、彼は覚悟を決めてリリアが待つ我が家へと足を向けた。リリアは、眠らずに洋介の帰りを待っていた。彼の顔を見るなり、彼女は、全てを察したようだった。
「⋯⋯森へ、行っていたのね。彼女に会いに」
リリアの声は静かだったが、その中には深い悲しみと諦めが滲んでいた。
洋介はリリアの前に膝をつき全てを話した。春音とのこと、前世での約束、そして彼女が自分のためにエルフであることをやめ、人間になったこと。
「リリア、すまない⋯⋯。俺は君を裏切ってしまった。どんな罵りも受ける覚悟だ」
リリアは黙って洋介の話を聞いていた。そして静かに涙を流した。
「⋯⋯薄々、気づいていたわ。あなたは私と一緒にいても、どこか遠くを見ていることが多かった。あなたの心の中に、別の女性がいることも。それが、あの森の女神様だったのね」
リリアは、涙を拭うと、毅然とした態度で、洋介を見つめた。
「⋯⋯息子は私が引き取ります。あなたはその人と、生きていきなさい。それが、あなたの本当の幸せなのでしょうから」
「リリア⋯⋯」
「ただし一つだけ約束して。息子の父親として時々は顔を見せに来てほしい。あの子から父親を奪わないで」
リリアの言葉は洋介にとって、何よりも辛いものだった。彼女の、あまりにも深い優しさが彼の罪悪感をさらに増幅させた。
その日から、洋介と春音の償いの日々が始まった。洋介はリリアと離婚し、村人たちから冷たい視線を浴びながらも、建築士としての仕事を誠実に続けた。彼は言葉ではなく、行動で村への貢献を示し続けるしかなかった。
春音もまた、村人たちから「夫を奪った、元エルフ」として、好奇と軽蔑の目で見られた。しかし彼女は決して下を向くことはなかった。持ち前の明るさと優しさで人々と接し続けた。畑仕事を手伝い、子供たちの面倒を見、病人がいれば人間としてできる精一杯の看病をした。
最初は遠巻きに見ていた村人たちも、二人の真摯な姿を見るうちに、少しずつ、その態度を軟化させていった。特にリリアが毅然として、二人を庇い続けたことが大きかった。
「あの二人は、確かに、過ちを犯したのかもしれない。でも彼らは、その罪を背負って、ここで生きていくことを決めたの。私たちに彼らを裁く権利はないわ」
リリアの言葉に、村人たちも次第に二人を受け入れていくようになった。
洋介と春音は、村はずれの小さな家で静かに愛を育んでいった。決して裕福ではない、質素な暮らし。しかし、そこには確かな幸福があった。
春音は、人間になったことで初めて空腹を覚え、疲れを感じ、風邪をひいた。その一つ一つが、彼女にとっては、新鮮な驚きであり喜びだった。洋介と、同じものを食べ、同じように眠りにつく。そんな当たり前の日常が、彼女にとっては、何よりも愛おしかった。
洋介もまた、春音といると心が安らいだ。彼女は彼の心の拠り所だった。仕事で疲れて帰ってきても、彼女の笑顔を見れば、疲れなど吹き飛んでしまう。
時々、洋介は息子に会いに、リリアの元を訪れた。息子はすくすくと成長し、洋介によく懐いた。リリアはいつも、笑顔で彼を迎えてくれたが、その笑顔の裏にある彼女の寂しさを思うと、洋介の胸は痛んだ。
春音も、そのことを十分に理解していた。彼女は決して、洋介とリリアの親子の時間を、邪魔しようとはしなかった。ただ、静かに、洋介の帰りを待ち、彼が父親としての責任を果たせるように支え続けた。
歳月が流れ、村はさらに豊かになった。洋介が設計した建物が次々と建てられていった。春音は、村の子供たちに文字や物語を教えるようになり、誰もが彼女を、「春音先生」と呼び、慕うようになった。
二人の顔には穏やかな、笑いジワが刻まれていった。それは二人が同じ時間を共に生きてきた、確かな証だった。
しかし、運命は時に、残酷な試練を与える。人間としての寿命という抗うことのできない現実が、すぐそこに迫っていることを、二人はまだ知らなかった。
「⋯⋯森へ、行っていたのね。彼女に会いに」
リリアの声は静かだったが、その中には深い悲しみと諦めが滲んでいた。
洋介はリリアの前に膝をつき全てを話した。春音とのこと、前世での約束、そして彼女が自分のためにエルフであることをやめ、人間になったこと。
「リリア、すまない⋯⋯。俺は君を裏切ってしまった。どんな罵りも受ける覚悟だ」
リリアは黙って洋介の話を聞いていた。そして静かに涙を流した。
「⋯⋯薄々、気づいていたわ。あなたは私と一緒にいても、どこか遠くを見ていることが多かった。あなたの心の中に、別の女性がいることも。それが、あの森の女神様だったのね」
リリアは、涙を拭うと、毅然とした態度で、洋介を見つめた。
「⋯⋯息子は私が引き取ります。あなたはその人と、生きていきなさい。それが、あなたの本当の幸せなのでしょうから」
「リリア⋯⋯」
「ただし一つだけ約束して。息子の父親として時々は顔を見せに来てほしい。あの子から父親を奪わないで」
リリアの言葉は洋介にとって、何よりも辛いものだった。彼女の、あまりにも深い優しさが彼の罪悪感をさらに増幅させた。
その日から、洋介と春音の償いの日々が始まった。洋介はリリアと離婚し、村人たちから冷たい視線を浴びながらも、建築士としての仕事を誠実に続けた。彼は言葉ではなく、行動で村への貢献を示し続けるしかなかった。
春音もまた、村人たちから「夫を奪った、元エルフ」として、好奇と軽蔑の目で見られた。しかし彼女は決して下を向くことはなかった。持ち前の明るさと優しさで人々と接し続けた。畑仕事を手伝い、子供たちの面倒を見、病人がいれば人間としてできる精一杯の看病をした。
最初は遠巻きに見ていた村人たちも、二人の真摯な姿を見るうちに、少しずつ、その態度を軟化させていった。特にリリアが毅然として、二人を庇い続けたことが大きかった。
「あの二人は、確かに、過ちを犯したのかもしれない。でも彼らは、その罪を背負って、ここで生きていくことを決めたの。私たちに彼らを裁く権利はないわ」
リリアの言葉に、村人たちも次第に二人を受け入れていくようになった。
洋介と春音は、村はずれの小さな家で静かに愛を育んでいった。決して裕福ではない、質素な暮らし。しかし、そこには確かな幸福があった。
春音は、人間になったことで初めて空腹を覚え、疲れを感じ、風邪をひいた。その一つ一つが、彼女にとっては、新鮮な驚きであり喜びだった。洋介と、同じものを食べ、同じように眠りにつく。そんな当たり前の日常が、彼女にとっては、何よりも愛おしかった。
洋介もまた、春音といると心が安らいだ。彼女は彼の心の拠り所だった。仕事で疲れて帰ってきても、彼女の笑顔を見れば、疲れなど吹き飛んでしまう。
時々、洋介は息子に会いに、リリアの元を訪れた。息子はすくすくと成長し、洋介によく懐いた。リリアはいつも、笑顔で彼を迎えてくれたが、その笑顔の裏にある彼女の寂しさを思うと、洋介の胸は痛んだ。
春音も、そのことを十分に理解していた。彼女は決して、洋介とリリアの親子の時間を、邪魔しようとはしなかった。ただ、静かに、洋介の帰りを待ち、彼が父親としての責任を果たせるように支え続けた。
歳月が流れ、村はさらに豊かになった。洋介が設計した建物が次々と建てられていった。春音は、村の子供たちに文字や物語を教えるようになり、誰もが彼女を、「春音先生」と呼び、慕うようになった。
二人の顔には穏やかな、笑いジワが刻まれていった。それは二人が同じ時間を共に生きてきた、確かな証だった。
しかし、運命は時に、残酷な試練を与える。人間としての寿命という抗うことのできない現実が、すぐそこに迫っていることを、二人はまだ知らなかった。
第十章:春の音、永遠に
春音が人間になってから五十年という歳月が流れた。洋介も春音も、すっかり腰の曲がった老人になっていた。洋介の髪は、真っ白になり、その手は長年の仕事で節くれ立っていた。春音の顔には深いシワが刻まれ、その足取りも、おぼつかなくなっていた。しかし、二人の間に流れる空気は、若い頃と少しも変わらなかった。縁側で日向ぼっこをしながらの昔話に花を咲かせる。それが二人の日課だった。
「ねえ、洋介さん。覚えてる? 私たちが初めて会った、ギャラリーのこと」
「ああ、覚えてるよ。君は目を輝かせて、俺の設計を褒めてくれたな」
「あの時から、私はあなたのことが好きだったのよ」
「俺もだよ、春音。君の笑顔に、一目で心を奪われた」
そんな穏やかな日々が、永遠に続くかのように思われた。
しかし、ある冬の日、春音は病に倒れた。ただの風邪だと思っていたが、咳は一向に収まらなかった。医者はもう手の施しようがないと、首を横に振った。
春音は、自分の死期が近いことを悟った。彼女は不思議と、穏やかな気持ちでその時を受け入れていた。
「洋介さん、悲しまないで。私は幸せだったわ。あなたと同じ人間として、同じ時間を生きることができて。本当に幸せだった」
ベッドの上で、弱々しく微笑む春音の手を、洋介は強く握りしめた。
「俺の方こそ幸せだったよ、春音。君が俺の人生にいてくれて、本当によかった」
涙が止まらなかった。彼女のいない世界で、これからどうやって生きていけばいいのか。
春音の容態は日増しに悪化していった。意識が朦朧とすることが多くなった。そんなある夜、春音はうわ言のように呟いた。
「⋯⋯森が⋯⋯私を、呼んでいる⋯⋯」
その言葉を聞いた洋介は、決心した。春音をあの森へ連れて行こう。彼女がエルフとして生まれた、あの場所へ。
洋介は村人たちの助けを借りて、春音を担架に乗せ、森へと向かった。リリアも成長した息子と共に、その後を、ついてきた。
森は五十年前と、変わらず、美しく、神秘的な空気に満ちていた。エルドランは森の入り口で、静かに一行を出迎えた。その姿もまた、以前と少しも変わっていなかった。
洋介はエルドランに、深く頭を下げた。
「エルドラン様、どうか春音を、この森で眠らせてはいただけないでしょうか」
エルドランは何も言わず、一行を森の奥深く、あの神聖な泉のほとりへと導いた。
春音は泉のほとりに、そっと横たえられた。彼女は薄っすらと目を開け、懐かしそうに周りを見渡した。
「⋯⋯ああ、懐かしい⋯⋯。ここで私はエリアーナとして生まれたのね⋯⋯」
春音は、洋介の手を弱々しく握った。
「洋介さん、ありがとう。最後に、ここに連れてきてくれて」
「春音⋯⋯」
「もう思い残すことはないわ。あなたと出会えて、本当によかった⋯⋯」
そう言うと、春音は、満足そうな笑みを浮かべ、静かに目を閉じた。彼女の手から、力が抜けていく。
「春音! 春音!」
洋介は何度も彼女の名前を叫んだが、もう返事はなかった。小田春音、享年八十二歳。彼女の人間としての長い旅が終わった瞬間だった。
洋介の悲痛な叫びが森に響き渡った。
その時、再び奇跡が起こった。春音の亡骸が柔らかな金色の光に包まれ始めたのだ。そして、その体はゆっくりと光の粒子となって空へと昇っていった。粒子は森の木々に降り注ぎ、森全体が一層輝きを増していくようだった。
「⋯⋯彼女は森に還ったのだ。森の一部となったのだ」
エルドランが静かに呟いた。
春音は死んでいなくなったのではなかった。彼女の魂はこの森と一体となり、永遠に生き続けるのだ。
その事実に洋介は慰めを見出した。彼は天を仰ぎ森に語りかけた。
「春音、聞こえるか。俺も、もうすぐそっちへ行く。そしたら、また一緒になろうな」
洋介はそれから数年後、春音の後を追うように静かに息を引き取った。彼の亡骸もまた、村人たちの手によってあの森へと運ばれ、春音が眠る泉のほとりに埋葬された。
今でもその森には二本の木が寄り添うように立っているという。一本は力強く天を突くように、もう一本はその幹に優しく、寄り添うように。そして、春になるとその木々には美しい花が咲き、風が吹くと、まるで春の音が聞こえてくるかのような優しい音色を奏でるのだという。
それは時を超え、種族を超えて愛を貫いた一組の男女の永遠の愛の物語。
「ねえ、洋介さん。覚えてる? 私たちが初めて会った、ギャラリーのこと」
「ああ、覚えてるよ。君は目を輝かせて、俺の設計を褒めてくれたな」
「あの時から、私はあなたのことが好きだったのよ」
「俺もだよ、春音。君の笑顔に、一目で心を奪われた」
そんな穏やかな日々が、永遠に続くかのように思われた。
しかし、ある冬の日、春音は病に倒れた。ただの風邪だと思っていたが、咳は一向に収まらなかった。医者はもう手の施しようがないと、首を横に振った。
春音は、自分の死期が近いことを悟った。彼女は不思議と、穏やかな気持ちでその時を受け入れていた。
「洋介さん、悲しまないで。私は幸せだったわ。あなたと同じ人間として、同じ時間を生きることができて。本当に幸せだった」
ベッドの上で、弱々しく微笑む春音の手を、洋介は強く握りしめた。
「俺の方こそ幸せだったよ、春音。君が俺の人生にいてくれて、本当によかった」
涙が止まらなかった。彼女のいない世界で、これからどうやって生きていけばいいのか。
春音の容態は日増しに悪化していった。意識が朦朧とすることが多くなった。そんなある夜、春音はうわ言のように呟いた。
「⋯⋯森が⋯⋯私を、呼んでいる⋯⋯」
その言葉を聞いた洋介は、決心した。春音をあの森へ連れて行こう。彼女がエルフとして生まれた、あの場所へ。
洋介は村人たちの助けを借りて、春音を担架に乗せ、森へと向かった。リリアも成長した息子と共に、その後を、ついてきた。
森は五十年前と、変わらず、美しく、神秘的な空気に満ちていた。エルドランは森の入り口で、静かに一行を出迎えた。その姿もまた、以前と少しも変わっていなかった。
洋介はエルドランに、深く頭を下げた。
「エルドラン様、どうか春音を、この森で眠らせてはいただけないでしょうか」
エルドランは何も言わず、一行を森の奥深く、あの神聖な泉のほとりへと導いた。
春音は泉のほとりに、そっと横たえられた。彼女は薄っすらと目を開け、懐かしそうに周りを見渡した。
「⋯⋯ああ、懐かしい⋯⋯。ここで私はエリアーナとして生まれたのね⋯⋯」
春音は、洋介の手を弱々しく握った。
「洋介さん、ありがとう。最後に、ここに連れてきてくれて」
「春音⋯⋯」
「もう思い残すことはないわ。あなたと出会えて、本当によかった⋯⋯」
そう言うと、春音は、満足そうな笑みを浮かべ、静かに目を閉じた。彼女の手から、力が抜けていく。
「春音! 春音!」
洋介は何度も彼女の名前を叫んだが、もう返事はなかった。小田春音、享年八十二歳。彼女の人間としての長い旅が終わった瞬間だった。
洋介の悲痛な叫びが森に響き渡った。
その時、再び奇跡が起こった。春音の亡骸が柔らかな金色の光に包まれ始めたのだ。そして、その体はゆっくりと光の粒子となって空へと昇っていった。粒子は森の木々に降り注ぎ、森全体が一層輝きを増していくようだった。
「⋯⋯彼女は森に還ったのだ。森の一部となったのだ」
エルドランが静かに呟いた。
春音は死んでいなくなったのではなかった。彼女の魂はこの森と一体となり、永遠に生き続けるのだ。
その事実に洋介は慰めを見出した。彼は天を仰ぎ森に語りかけた。
「春音、聞こえるか。俺も、もうすぐそっちへ行く。そしたら、また一緒になろうな」
洋介はそれから数年後、春音の後を追うように静かに息を引き取った。彼の亡骸もまた、村人たちの手によってあの森へと運ばれ、春音が眠る泉のほとりに埋葬された。
今でもその森には二本の木が寄り添うように立っているという。一本は力強く天を突くように、もう一本はその幹に優しく、寄り添うように。そして、春になるとその木々には美しい花が咲き、風が吹くと、まるで春の音が聞こえてくるかのような優しい音色を奏でるのだという。
それは時を超え、種族を超えて愛を貫いた一組の男女の永遠の愛の物語。
他の小説も読みたいなら↓
- 長編小説 – 転生した春の音
- 長編小説 – 異世界への招待状 おじさんはそれなりにがんばる
- 短編小説 – 夏の1ページ
- 短編小説 – イニチャリD ~ 峠の疾風:自転車レーサーたちの物語 ~
- 短編小説 – メッセージ
- 短編小説 – 夢への挑戦
- 短編小説 – サイバーシャドウ
- 短編小説 – 雨の日の約束
- 短編小説 – FPSゲーマーの挑戦
- 短編小説 – 帰り道の出会い
- 短編小説 – マグニチュード7.5
- 短編小説 – 小さな町のパン屋さん
- 短編小説 – 大きな桜の木の下で
- 短編小説 – 風の囁(ささや)き
- 短編小説 – 命が吹き込まれたスリッパ
- 短編小説 – 消えた動画配信者
- 短編小説 – 幽霊屋敷
- 短編小説 – 地球消滅
- 短編小説 – VRが紡ぐ新たな現実
- 長編小説 – デスゲーム
- 短編小説 – ある一匹の猫の物語
- 短編小説 – 不可解な田舎町
- 短編小説 – 特売キャベツ
- 短編小説 – 世代を超えた友情
- 短編小説 – 星降る夜の秘密
-
前の記事

長編小説 – 異世界への招待状 おじさんはそれなりにがんばる 2025.06.18
-
次の記事

小説家になろうサイトを縦書きで読みたい時は!? 2025.08.20





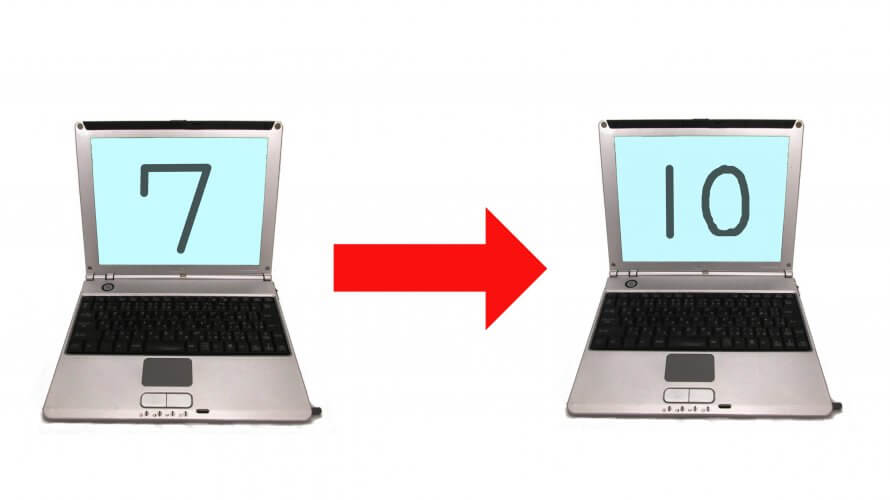








コメントを書く