短編小説 – ある一匹の猫の物語

都会の片隅、静かな路地裏にその猫はいた。名前もなく、誰のものでもない彼は、日々の糧を求めてゴミ箱を漁り、通行人の足元をすり抜けながら生きていた。
黒と白の模様を持つその野良猫は、人間に対して警戒心を持ちながらも、どこか寂しげな目をしていた。
彼が生まれたのは、古びた倉庫の裏手にある段ボール箱の中だった。母猫と兄弟たちと共に過ごした短い幼少期。しかし、母猫が突然姿を消し、兄弟たちも散り散りになった。
その日から彼は一匹で生き抜く術を学び、厳しい現実に立ち向かうことを余儀なくされた。
ある秋の夕暮れ、彼はいつものように路地裏を歩いていた。その日は特に冷え込んでおり、腹も空いていた。
そんな時、一人の女性が彼に気づいた。彼女は買い物袋を手に持ちながら、そっとしゃがみ込んで猫に声をかけた。
「寒いね、お腹空いてる?」
その声は柔らかく、どこか温かみがあった。
彼は一瞬だけ女性を見つめたが、すぐに背を向けて逃げようとした。しかし、その女性は急ぐことなく、袋から小さな缶詰を取り出し、路地の片隅に置いた。
「無理しなくていいよ。でも、もしお腹が空いてたら食べてね。」
女性はそれ以上近づくことなく、その場を去った。
しばらくしてから彼は缶詰の匂いに誘われ、恐る恐る近づいていった。それは今まで食べたことのない美味しい匂いだった。お腹が空いてた彼はその匂いに耐えきれずいつの間にか食べてしまっていた。
それから数日間、女性は毎日同じ時間に路地裏へやってきた。そして缶詰や水を置き、少し離れた場所で静かに待っていた。
彼女は決して急ぐことなく、猫が自分の存在に慣れるまで辛抱強く待った。最初は距離を保ちながらも餌だけを食べていた彼だったが、次第に女性の存在に慣れていった。そしてある日、彼女が差し出した手を警戒しながらも匂いを嗅ぎ、その手にそっと顔をこすりつけた。
その瞬間、彼女の顔には優しい笑みが浮かんだ。
「やっと触らせてくれたね。これからよろしくね。」
その日から二人の間には小さな信頼関係が生まれた。
だが、冬が近づくとともに、路地裏の生活はますます厳しくなった。寒さと空腹が彼を苦しめる中、女性はついにある提案をする。
「うちに来ない?暖かい場所で一緒に過ごそう。」
女性は小さなキャリーケースを用意し、中に柔らかい毛布を敷いていた。彼女の声には真剣さと優しさが混じっていた。
しかし、野良猫として生きてきた彼には、その提案がどこか不安でもあった。自由を失うことへの恐れ、人間との生活への未知なる不安。それでも寒さと飢えには勝てず、彼女との今までの信頼関係を信じ、彼は恐る恐るキャリーケースの中へ入った。
女性の家は小さなアパートだったが、暖かく清潔で居心地が良かった。彼女はまず彼をお風呂に入れ、長年の汚れやノミを落とした。猫は水が嫌いなのは彼女は知っているのか、洗う手つきがとても良かった。
その後、美味しい餌と水を与えてくれ、さらには新しい寝床を用意してくれた。
しかし、新しい環境に慣れるには時間が必要だった。
最初の数日は隅っこでじっとしていることが多かった彼だが、徐々に部屋の中を探索し始めた。
そして女性が撫でる手にも少しずつ心を開いていった。
「君の名前はどうしようかな……そうだ、『ハル』ってどう?」
春を迎えるような新しい生活の始まりを願って、彼女はそう名付けた。
その名前には優しさと希望が込められていた。
ハルとして新しい生活を始めた彼は、次第に家猫としての暮らしに馴染んでいった。
毎日の食事や暖かい寝床、人間との触れ合い。それはこれまで経験したことのない安心感だった。そしてなにより彼女が見せる笑顔がこの上なく嬉しかった。
時折窓から外を見ることもあったが、そこにはもうかつての孤独な路地裏ではなく、自分を見守ってくれる新しい家族がいるという実感があった。
そして彼は思った。
「ここが自分の居場所だ」と。
こうして一匹の野良猫だったハルは、人間との信頼関係を築き、新しい家族として迎え入れられた。
彼の目にはもう孤独や不安ではなく、穏やかな幸福が映っている。
あとがき
猫は慣れるまでが大変。人と猫の共存は最初が肝心。テレビでよくやっている保護猫を見ているとつくづくそう思う。
ある程度そこは端折ってますので、あしからず
- 長編小説 – 転生した春の音
- 長編小説 – 異世界への招待状 おじさんはそれなりにがんばる
- 短編小説 – 夏の1ページ
- 短編小説 – イニチャリD ~ 峠の疾風:自転車レーサーたちの物語 ~
- 短編小説 – メッセージ
- 短編小説 – 夢への挑戦
- 短編小説 – サイバーシャドウ
- 短編小説 – 雨の日の約束
- 短編小説 – FPSゲーマーの挑戦
- 短編小説 – 帰り道の出会い
- 短編小説 – マグニチュード7.5
- 短編小説 – 小さな町のパン屋さん
- 短編小説 – 大きな桜の木の下で
- 短編小説 – 風の囁(ささや)き
- 短編小説 – 命が吹き込まれたスリッパ
- 短編小説 – 消えた動画配信者
- 短編小説 – 幽霊屋敷
- 短編小説 – 地球消滅
- 短編小説 – VRが紡ぐ新たな現実
- 長編小説 – デスゲーム
- 短編小説 – ある一匹の猫の物語
- 短編小説 – 不可解な田舎町
- 短編小説 – 特売キャベツ
- 短編小説 – 世代を超えた友情
- 短編小説 – 星降る夜の秘密
-
前の記事

短編小説 – 不可解な田舎町 2025.03.17
-
次の記事

長編小説 – デスゲーム 2025.03.19





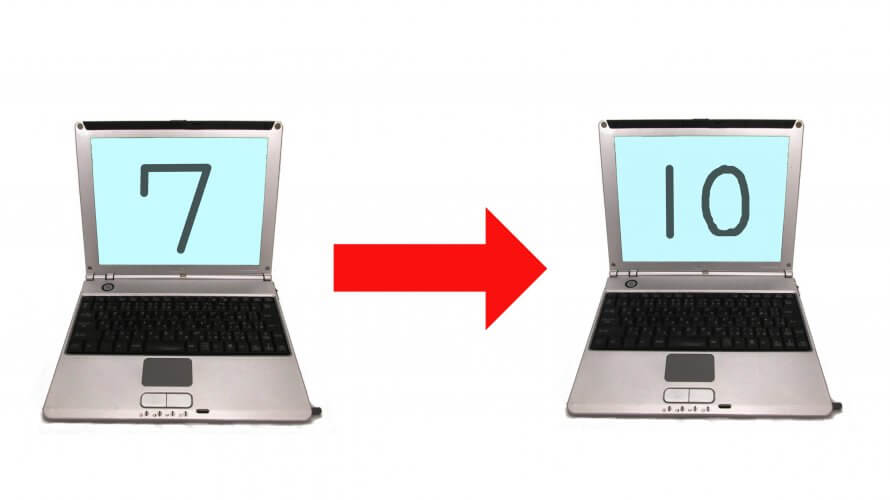








コメントを書く